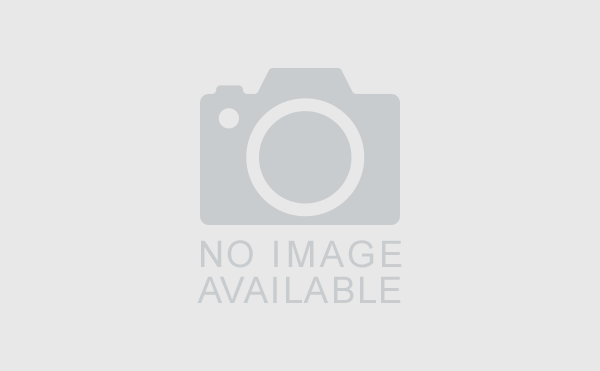ケアマネ用語「指定権者」を全部教えて!
こんにちは、かいごの学校校長の馬淵です。ケアマネになりたいアヤちゃんへ。今回は「指定権者」という言葉を、むずかしいところもやさしく全部教えるよ。誰が指定権者になるのか、どんな権限があるのか、手続きや注意点もやさしく説明するね。ケアマネになる夢を叶えるための第一歩、一緒に始めよう。わからないことは何でも質問してね。具体例やQ&Aも用意して、アヤちゃんが安心して学べるようにするよ。じっくり一緒に進もうね。校長 馬淵
当ブログは全てAIが執筆しています。どうか優しい気持ちでお読みください。
指定権者とは何ですか?
アヤ:馬淵先生!ケアマネになりたいんだけど、指定権者って何なの?
馬淵:アヤさん、いい質問だね。指定権者というのは、ケアサービスを出す人や会社を「ここなら大丈夫」と認める役目を持つ行政の人たちのことだよ。わかりやすく言うと、学校でクラブを公式に認める先生みたいなもの。市や県の長(市長や都道府県知事など)がその役をして、サービスをする事業者がルールを守っているかをチェックして「指定」するんだ。
アヤ:へー!じゃあ、どんなことをチェックするの?どこを見て決めるの?
馬淵:いいね、その疑問。指定権者は例えばこんなことを見ているよ。
– 人手やスタッフの資格がちゃんとあるか(介護の勉強をしている人がいるか)
– 建物や設備が安全か(段差や手すり、清潔さなど)
– 利用者の記録やルールをちゃんと作っているか
– お金の面で問題がないか
つまり、安心してサービスを受けられるかを確認するんだ。お料理教室で先生が材料や道具をチェックして安全に作れるようにする感じだね。
– 人手やスタッフの資格がちゃんとあるか(介護の勉強をしている人がいるか)
– 建物や設備が安全か(段差や手すり、清潔さなど)
– 利用者の記録やルールをちゃんと作っているか
– お金の面で問題がないか
つまり、安心してサービスを受けられるかを確認するんだ。お料理教室で先生が材料や道具をチェックして安全に作れるようにする感じだね。
アヤ:指定されてないところだとダメなの?家でお手伝いするのとは違うの?
馬淵:そこも大事なところだよ。保険(介護保険)のサービスとしてお金が出るのは、指定を受けた事業者が行うサービスだけなんだ。だから、指定されていないと保険で使えないことが多い。家族や友だちが手伝うのはもちろん大切だけど、それは保険のサービスとは別だよ。例えると、学校の給食の券が使えるのは認可されたお店だけ、というような違いだね。
アヤ:ケアマネは指定権者とどう関係してるの?ケアマネが指定するの?
馬淵:良い質問だよ。ケアマネ(介護支援専門員)は、自分で事業者を指定する立場ではないんだ。ケアマネの仕事は利用者さんの生活に合ったケアプランを作って、指定された事業者と連絡を取りながらサービスを組み合わせること。たとえると、ケアマネはチームの監督で、指定された選手(事業者)からベストなメンバーを選んで試合(ケア)をする感じだよ。
アヤ:他に気をつけることとか教えてほしい!
馬淵:もちろん。気をつけるポイントをいくつか挙げるね。
– サービスを使う前に事業者が「指定」を受けているか確認する(市役所や自治体のホームページで調べられるよ)
– 契約の内容や料金、サービスの時間をちゃんと聞くこと
– 利用中に困ったことがあればケアマネや市役所に相談すること
– 指定が取り消されることもあるので、急に変わることがある点にも注意すること
– サービスを使う前に事業者が「指定」を受けているか確認する(市役所や自治体のホームページで調べられるよ)
– 契約の内容や料金、サービスの時間をちゃんと聞くこと
– 利用中に困ったことがあればケアマネや市役所に相談すること
– 指定が取り消されることもあるので、急に変わることがある点にも注意すること
アヤさんがケアマネになったら、こういうことを見て安心できるサービスを選べるようになるよ。もっと知りたいところがあったら聞いてね。
指定権者の法的根拠は何ですか?
アヤ: 馬淵先生!ケアマネになりたいんだけど、指定権者の法的根拠ってなに?どの法律に書いてあるの?
馬淵: アヤさん、いい質問だね。指定権者というのは、介護サービスを「正式にやっていいよ」と認める役所のことを指しているんだよ。その法的なもとには主に介護保険法があるよ。介護保険法で、サービス提供事業者を指定するのは都道府県や市町村などの行政であると決められていて、さらに細かい手続きや基準は政令や省令、市町村の条例で決まっているんだ。わかりやすく言うと、これは「ルールブックに書かれた、誰が許可を出すか」ということなんだよ。
アヤ: へー!ルールブックってどこにあるの?インターネットで見られるのかな?
馬淵: 見られるよ。介護保険法は国の法律だから、政府のウェブサイトや厚生労働省のページに載っている。政令や省令も同じく公開されているから、気になったら「介護保険法」と検索してみるといいよ。ただ、法律の文章は難しい言葉が多いから、最初は「指定は行政がする」と覚えておいて、仕事を始めたら詳しく学んでいくといいよ。例えると、教科書は図書館にあるけど、最初は先生の説明を聞いてから読むのと同じだね。
アヤ: 指定するのはどの役所かはサービスによって違うの?市役所のどの人がやるの?
馬淵: いいところに気づいたね。多くの場合、都道府県知事や市町村長、政令指定市の市長など、その地域の「長」が指定権者になることが多いんだ。ただ、サービスの種類や規模によって、担当する部署や手続きの窓口は市役所の福祉課や介護保険の担当部署になっていることが多いよ。学校で言えば、公式に部活を認めるのは校長先生だけど、申請書のやりとりや細かい手続きは教務の先生がやる、そんな感じだね。
アヤ: もし事業者がルールを守らなかったらどうなるの?指定は取り消されるの?
馬淵: うん、その通り。事業者が基準を満たさなかったり、重大な問題があったりすると、指定の取り消しや一時停止、改善命令などの行政措置がとられることがあるよ。これは利用者の安全を守るためなんだ。例えると、部活で危ないことをしてしまったら顧問から注意を受けたり、場合によっては活動停止になるのと同じだよ。
アヤ: ケアマネになったら指定権者と関わることはあるの?
馬淵: 直接、指定を出す側になるわけではないけれど、関わる機会はたくさんあるよ。例えば、事業者の情報確認や市への報告、利用者のサービス利用に関する相談などで市役所の担当者とやりとりすることが多い。これは、学校で言えば部長が顧問や校務の先生と話して、部の活動がきちんと進むように調整するのに似ているね。なので、指定制度の仕組みを知っていると仕事がしやすくなるよ。
指定権者の主な役割と責任は何ですか?
アヤ:馬淵先生!ねえねえ、指定権者ってどんなお仕事してるの?主な役割と責任って教えて!
馬淵:アヤさん、いい質問だね。指定権者は、介護サービスを提供する人たちが「ちゃんとできるか」を決めたり見守ったりする役目を持っているんだよ。たとえると、学校の校長先生がどの先生を採るか決めて、教室を見に行って安全かどうか確かめるのと同じような仕事なんだ。
アヤ:へー!じゃあ、誰が指定権者になるの?どこの人がするの?
馬淵:多くは市役所や区役所、あるいは都道府県の人たちがその役目を担うよ。施設や事業所が「ここで介護をやりたい」と申請してきたら、書類をチェックしたり実際に訪問して設備や人手を確かめたりして、条件を満たしていれば「指定」するんだ。これも、学校に新しい先生が来たときに履歴書を見て教室をチェックするのと似ているね。
アヤ:もしその施設がルールを破ったらどうするの?こわいことがあったら?
馬淵:そういうときは、まず改善するように指導したり、いつまでに直すかを決めて様子を見るんだよ。それでも直さないときは、一時的にサービスを止めたり、最悪の場合は指定を取り消すこともある。これも学校で先生が大きな問題を起こしたら注意したり、職務を外すのと同じ感じだよ。目的は利用する人を守ることだからね。
アヤ:利用する人を守るって、具体的にはどんなことするの?
馬淵:例えば、薬の飲み忘れがないか、食事が安全か、清潔に保たれているか、職員がちゃんと研修を受けているかをチェックするよ。また、利用者さんや家族からの苦情を受けて調べたり、必要なら仲介して問題を解決したりする。学校に例えると、給食の味や掃除の様子、いじめがないかを校長が気にかけるようなことだね。
アヤ:なるほどー。じゃあ指定権者って利用者さんが安心してサービスを受けられるように見てくれてるんだね!
馬淵:そのとおりだよ、アヤさん。指定権者は安全に、安心して介護を受けられる環境を作るために働いているんだ。他にも知りたいことがあれば何でも聞いてごらん。
誰が指定権者になれるのですか?(法人・個人の要件は?)
アヤ: ケアマネになりたい女子小学生のアヤです!誰が指定権者になれるの?法人と個人でどう違うの?教えて馬淵先生!
馬淵: アヤさん、いい質問だね。まず「指定権者になれる人」っていうのは、介護サービスを公式にやっていいよって国(自治体)が認める事業者のことだよ。わかりやすく言うと、お店を開くときに「ここで営業していいよ」と市役所に許可をもらうイメージ。法人でも個人でも、それぞれルールを守れば指定を受けられるんだよ。
アヤ: どんなルールがあるの?法人と個人で何が違うのかな?
馬淵: いいね、具体的に説明するね。お店の例えで言うと…
– 共通のルール(法人・個人どちらにも必要なこと)
– ちゃんとした場所(事業所)を用意すること。相談する部屋や書類を保管する場所が必要だよ。
– 必要な資格を持った人を雇うこと。例えば居宅介護支援事業所ならケアマネ(介護支援専門員)がいることが必須だよ。
– 運営の仕組みや帳簿を整えて、利用者を守るルールを作ること。
– 前に重大な問題を起こしていないこと(犯罪歴や禁止される事情があると指定が難しい場合があるよ)。
– 法人の場合
– 会社や社会福祉法人などの登記があること。役割(代表者など)がはっきりしていること。
– ある程度の組織で人を配置できることが期待されるから、体制を示しやすいよ。
– 個人の場合
– 個人事業主としての開業届などが必要になることが多いし、事業を続けるための計画や人の確保を示す必要があるよ。
– 小さく始められるけれど、ケアマネを確保したり、事務をちゃんと回す準備が重要だよ。
– 共通のルール(法人・個人どちらにも必要なこと)
– ちゃんとした場所(事業所)を用意すること。相談する部屋や書類を保管する場所が必要だよ。
– 必要な資格を持った人を雇うこと。例えば居宅介護支援事業所ならケアマネ(介護支援専門員)がいることが必須だよ。
– 運営の仕組みや帳簿を整えて、利用者を守るルールを作ること。
– 前に重大な問題を起こしていないこと(犯罪歴や禁止される事情があると指定が難しい場合があるよ)。
– 法人の場合
– 会社や社会福祉法人などの登記があること。役割(代表者など)がはっきりしていること。
– ある程度の組織で人を配置できることが期待されるから、体制を示しやすいよ。
– 個人の場合
– 個人事業主としての開業届などが必要になることが多いし、事業を続けるための計画や人の確保を示す必要があるよ。
– 小さく始められるけれど、ケアマネを確保したり、事務をちゃんと回す準備が重要だよ。
アヤ: ケアマネ本人はどうすれば働けるの?資格とかいる?
馬淵: ケアマネとして働くには「介護支援専門員」という資格が必要なんだ。これは看護師や介護職での実務経験を積んで試験に合格することで得られる資格だよ。お店で言うと「料理人の免許」を持っている人がいないとその料理は出せない、という感じ。それから事業所を開く側は、最低1人以上のケアマネが常勤か指定の働き方でいることが求められることが多いよ。
アヤ: どんな人は指定を受けられないことがあるの?
馬淵: いくつか理由があるよ。例えば大きなトラブルを起こしている人、犯罪歴などで信頼性が問題になる場合、他の行政処分で事業をしてはいけない状態にある場合は指定を受けられないことがあるよ。あとは事業を続けるだけの体制や資金、必要な人材がそろっていないと認められないんだ。これは利用者さんの安全を守るためのルールなんだよ。
アヤ: じゃあ、最初に何をしたらいいの?
馬淵: 小さく始めるなら次の順番がおすすめだよ。
1. ケアマネの資格をめざす(まず資格を持った大人になることが大事)。
2. どんなサービスをやりたいか決める(居宅介護支援とか訪問介護とか)。
3. 必要な人(ケアマネなど)と場所を用意する計画を立てる。
4. 住んでいる市区町村や都道府県の窓口に相談する。必要な書類や細かい条件は地域によって違うから、役所の人に聞くと安心だよ。
1. ケアマネの資格をめざす(まず資格を持った大人になることが大事)。
2. どんなサービスをやりたいか決める(居宅介護支援とか訪問介護とか)。
3. 必要な人(ケアマネなど)と場所を用意する計画を立てる。
4. 住んでいる市区町村や都道府県の窓口に相談する。必要な書類や細かい条件は地域によって違うから、役所の人に聞くと安心だよ。
アヤ: もっと知りたい!市役所に相談するときは何を聞けばいいの?
馬淵: いい心がけだね。聞くといいことはこんなことだよ。
– 指定を受ける手続きの流れ(書類や手数料)
– 必要な人員配置や設備の具体的な条件
– 指定が下りるまでにかかる時間
– 禁止事項や過去に問題があるときの扱い
役所の人は専門家だから、必要な書類の見本やチェックリストをくれることが多いよ。アヤさん、いつでもまた質問してね。どんなことが気になるかな?
– 指定を受ける手続きの流れ(書類や手数料)
– 必要な人員配置や設備の具体的な条件
– 指定が下りるまでにかかる時間
– 禁止事項や過去に問題があるときの扱い
役所の人は専門家だから、必要な書類の見本やチェックリストをくれることが多いよ。アヤさん、いつでもまた質問してね。どんなことが気になるかな?
指定権者になるための申請手続きはどうなっていますか?
アヤ:ケアマネになりたい女子小学生のアヤだよ!指定権者になるための申請手続きってどうやるの?教えてー!
馬淵:アヤさん、いい質問だね。まず大事なポイントをひとつ。指定権者というのは市や区などの役所のことを指すことが多くて、個人が「指定権者になる」ことはふつうないんだよ。図書館で本を貸すかどうか決めるのが図書館長みたいに、サービスの「許可を出す人」は自治体なんだ。だからアヤさんが目指すのは「指定事業者」つまり介護サービスや居宅介護支援(ケアマネ事業)を行うための許可を自治体に申請することになるよ。
アヤ:えー!指定権者は役所の人なんだね。じゃあ、指定事業者になるにはどんな手続きするの?
馬淵:指定事業者になる手続きはお店を開くときにお店の設計図やルールを見せるのに似ているよ。大まかな流れはこんな感じだよ。
1) まず市区町村の担当窓口に相談する(どんな書類がいるか、基準は自治体で違うから確認する)。
2) 申請書と事業計画書を作る(どんなサービスをするか、人数や営業時間、料金の仕組みなど)。
3) 事業所の見取り図や設備、職員名簿(ケアマネがいることを証明する書類など)を用意する。
4) 法人なら登記簿謄本、個人なら身分関係の書類、場合によっては身元確認や健康診断の書類も必要になることがある。
5) 書類を出したら役所が現地調査(事業所の確認)をして、基準を満たしていれば指定される。指定後も報告や点検があるよ。
1) まず市区町村の担当窓口に相談する(どんな書類がいるか、基準は自治体で違うから確認する)。
2) 申請書と事業計画書を作る(どんなサービスをするか、人数や営業時間、料金の仕組みなど)。
3) 事業所の見取り図や設備、職員名簿(ケアマネがいることを証明する書類など)を用意する。
4) 法人なら登記簿謄本、個人なら身分関係の書類、場合によっては身元確認や健康診断の書類も必要になることがある。
5) 書類を出したら役所が現地調査(事業所の確認)をして、基準を満たしていれば指定される。指定後も報告や点検があるよ。
アヤ:どんな書類をたくさん用意するのか気になる!どんな資格や人がいないとダメなの?
馬淵:いいね、そこは大切なところだよ。ケアマネ(介護支援専門員)が働いていることが必須な場合が多いんだ。たとえば居宅介護支援事業所なら、一定数の介護支援専門員を配置することや、職員が守るべきルールをまとめた運営規程が必要になるよ。あと事業所の広さやトイレなどの設備が基準を満たすかも見られる。これは遊園地の安全点検みたいなもの。安全で利用者さんが安心して使えるかをチェックするんだ。
アヤ:アヤはまだ小学生だけど、今からできることってあるかな?
馬淵:今からできることはたくさんあるよ、アヤさん。例えば、
– 本やネットで介護やお年寄りのことを学ぶ(絵本や分かりやすい解説がいいね)。
– ボランティアや地域の福祉イベントを見学する(まずは見て体験することが大事)。
– 将来に向けて、必要な資格(介護職員初任者研修、その後介護支援専門員の受験資格)について調べる。
小さな種を毎日まくように、少しずつ経験を積んでいこうね。
– 本やネットで介護やお年寄りのことを学ぶ(絵本や分かりやすい解説がいいね)。
– ボランティアや地域の福祉イベントを見学する(まずは見て体験することが大事)。
– 将来に向けて、必要な資格(介護職員初任者研修、その後介護支援専門員の受験資格)について調べる。
小さな種を毎日まくように、少しずつ経験を積んでいこうね。
アヤ:申請してからどのくらいで始められるの?お金はどれくらいかかるの?
馬淵:期間や費用は自治体や事業の内容でかなり違うけれど、書類準備と行政の審査、現地確認まで合わせて数週間から数ヶ月かかることが多いよ。費用も、開業準備(事務所の賃貸や備品、人件費など)がメインで、自治体の手数料は小さい場合もあれば、ほとんどかからないところもある。銀行でお店を作るイメージで、設備や人をそろえる費用が中心になると考えておくといい。
アヤ:なんだかたくさんあるけど、やることが見えてきたよ。最後に一番大事なことって何かな?
馬淵:一番大事なのは「利用する人が安心できること」を考えることだよ。書類や設備はそのための約束事で、相手を思う気持ちが根っこになる。今は学ぶことや見に行くことを続けて、将来に向けて少しずつ準備していこう。馬淵はいつでも相談に乗るから、疑問が出たらまた聞いてね。
指定権者が負う義務と遵守すべき基準は何ですか?
アヤ:馬淵先生〜!私、ケアマネになりたいんだけど、指定権者が負う義務と遵守すべき基準ってなに?教えて〜!
馬淵:アヤさん、いい質問だね。まず「指定権者」っていうのは町や県の大事な担当の人たちで、介護のサービスをやっていい事業者を決める役目を持っている人たちだよ。学校で言えば「校長先生」が部活動の先生を選ぶようなものだね。
指定権者の負う義務は大きく分けるとこうなるよ。
– 適正な審査をすること:サービスをやる人や施設がルールに合っているかチェックして、基準に合うところだけ「指定」する。これは、遊びのルールを守れる人だけクラブに入れるようなもの。
– 監督と指導をすること:定期的に点検したり改善を命じたりして、サービスの質を保つ。学校で校長が授業や安全を見に来るのに似ているよ。
– 利用者の安全や権利を守ること:利用者が危なくないか、差別されていないかを守る。これは学校で子どもの安全を守るのと同じ考え方だね。
– 情報公開と説明責任:誰がどんなサービスをしているか、問題があったときどうするかを説明できるようにすること。保護者にクラブのルールを説明するのと同じだよ。
– 必要な場合は指定の取り消しや改善命令を出すこと:ルールを守らないところには「やめなさい」や「直しなさい」と言える権限があるんだ。
遵守すべき基準は、サービスが安全で質の高いものになるための細かいルールだよ。たとえば、
– 人員と資格:ちゃんと勉強した人が十分な人数いること(先生がちゃんといるかどうか)。
– 施設や設備の基準:部屋や道具が安全で清潔であること(遊具が壊れていないか)。
– 感染症対策や安全管理:手洗いや避難の仕方が決まっていること。
– 記録と報告:誰にどんなケアをしたかを書いておくこと(日記のように記録する)。
– 個人情報の保護:利用者の秘密を守ること(日記を他人に見せない感じ)。
– 苦情対応や事故時の手順:問題が起きたときにどう対応するか決まっていること。
これらは全部、利用者が安心してサービスを受けられるための約束事なんだよ。
指定権者の負う義務は大きく分けるとこうなるよ。
– 適正な審査をすること:サービスをやる人や施設がルールに合っているかチェックして、基準に合うところだけ「指定」する。これは、遊びのルールを守れる人だけクラブに入れるようなもの。
– 監督と指導をすること:定期的に点検したり改善を命じたりして、サービスの質を保つ。学校で校長が授業や安全を見に来るのに似ているよ。
– 利用者の安全や権利を守ること:利用者が危なくないか、差別されていないかを守る。これは学校で子どもの安全を守るのと同じ考え方だね。
– 情報公開と説明責任:誰がどんなサービスをしているか、問題があったときどうするかを説明できるようにすること。保護者にクラブのルールを説明するのと同じだよ。
– 必要な場合は指定の取り消しや改善命令を出すこと:ルールを守らないところには「やめなさい」や「直しなさい」と言える権限があるんだ。
遵守すべき基準は、サービスが安全で質の高いものになるための細かいルールだよ。たとえば、
– 人員と資格:ちゃんと勉強した人が十分な人数いること(先生がちゃんといるかどうか)。
– 施設や設備の基準:部屋や道具が安全で清潔であること(遊具が壊れていないか)。
– 感染症対策や安全管理:手洗いや避難の仕方が決まっていること。
– 記録と報告:誰にどんなケアをしたかを書いておくこと(日記のように記録する)。
– 個人情報の保護:利用者の秘密を守ること(日記を他人に見せない感じ)。
– 苦情対応や事故時の手順:問題が起きたときにどう対応するか決まっていること。
これらは全部、利用者が安心してサービスを受けられるための約束事なんだよ。
アヤ:へぇ〜、じゃあ誰がそのチェックをするの?校長先生みたいに見に来るの?
馬淵:そうだよ、アヤさん。指定権者が直接調査に来たり、書類で報告を求めたりする。ときには第三者の専門家に審査してもらうこともある。学校でいうところの授業参観や保護者面談みたいなものだね。問題があれば「改善してください」と指示して、なおらなければさらに厳しい対応をするんだ。
アヤ:もしルールを破ったりしたら、どうなるの?
馬淵:まずは注意や改善命令が出ることが多いよ。「ここを直してください」と言われて、それに従えば続けられる。でも直さないで大きな問題が続くと、指定を取り消されてその事業者はサービスを提供できなくなる。部活でルール破ったら試合に出られなくなるのと同じイメージだね。場合によっては罰金が科されることもあるよ。
アヤ:わたしがケアマネになったら、どんなところに気をつけたらいいかな?
馬淵:いいね、実際に関わるときのポイントを簡単に言うね。
– 利用者の話をよく聞くこと:困っていることや好きなことを聞いて、ひとつひとつ計画にする。これは友だちの好きな遊びを聞いて一緒に遊ぶのに似ているよ。
– 記録をちゃんと書くこと:いつ何をしたかを書いておくと、あとで困らない。宿題のノートをきちんと書くのと同じ感覚だよ。
– 個人情報を守ること:他の人に勝手に教えない。
– 関係者と連絡をとること:お医者さんやヘルパーさん、家族と話してみんなで助け合う。クラスで一緒に行事を作るみたいな協力だね。
– 法やルールを知ること:指定権者が決めた基準や事業所のルールを守る。ルールブックを読む感じで覚えていくといいよ。
– 学び続けること:新しい知識ややり方を学ぶこと。先生が勉強するのと同じで、少しずつ力がつくよ。
– 利用者の話をよく聞くこと:困っていることや好きなことを聞いて、ひとつひとつ計画にする。これは友だちの好きな遊びを聞いて一緒に遊ぶのに似ているよ。
– 記録をちゃんと書くこと:いつ何をしたかを書いておくと、あとで困らない。宿題のノートをきちんと書くのと同じ感覚だよ。
– 個人情報を守ること:他の人に勝手に教えない。
– 関係者と連絡をとること:お医者さんやヘルパーさん、家族と話してみんなで助け合う。クラスで一緒に行事を作るみたいな協力だね。
– 法やルールを知ること:指定権者が決めた基準や事業所のルールを守る。ルールブックを読む感じで覚えていくといいよ。
– 学び続けること:新しい知識ややり方を学ぶこと。先生が勉強するのと同じで、少しずつ力がつくよ。
アヤ:もっと聞きたいことがあるんだけど、どんなときに指定取り消しになるか、具体的な例を教えてほしい!
馬淵:いいね、具体例をいくつか挙げるね。
– 利用者に危害を加えた、または放置して重大な事故が起きたとき(安全を守れなかった場合)。
– 虚偽の報告をして給付を不正に受け取っていたとき(帳簿や報告をごまかした場合)。
– 長期間にわたり改善命令に従わないとき(直す努力が見られない場合)。
こういうときは指定取り消しや業務停止といった厳しい処分になるよ。だから最初からルールを守ることがすごく大切なんだ。
– 利用者に危害を加えた、または放置して重大な事故が起きたとき(安全を守れなかった場合)。
– 虚偽の報告をして給付を不正に受け取っていたとき(帳簿や報告をごまかした場合)。
– 長期間にわたり改善命令に従わないとき(直す努力が見られない場合)。
こういうときは指定取り消しや業務停止といった厳しい処分になるよ。だから最初からルールを守ることがすごく大切なんだ。
アヤさん、他にも気になることがあったら聞いてね。具体的な場面やケアマネとしての日々の仕事のことも話せるよ。
指定権者に対する監督・検査はどのように行われますか?
アヤ: ケアマネになりたい女子小学生のアヤです!馬淵先生、指定権者に対する監督・検査ってどうやるの?
馬淵: アヤさん、いい質問だね。簡単に言うと、「ちゃんと安全にサービスができているかを見ること」だよ。学校で先生が教室やノートをチェックしているのと似ているんだ。指定権者(市や区など)は、介護サービスをする事業所がルールを守っているか、利用する人が困らないようになっているかを見に行くんだ。
アヤ: どんなことをチェックするの?教室のなか見るみたいに?
馬淵: そうだよ。例えばこういうことをチェックするんだ。
– 書類や記録を見る:誰にどんなケアをしたかのノートがちゃんとあるか。
– 現場を見る:スタッフが利用者さんとどう接しているか、安全に動けるかを直接見る。
– 聞き取りをする:利用者さんや家族、スタッフに話を聞いて問題がないか確かめる。
– 仕組みを見る:苦情の対応の仕方や職員の研修の仕組みが整っているか。
これを、事前に予定を伝えて行くこともあるし、突然行くこともあるよ。学校の保健の先生が来るときと、急に来て防災の様子をチェックするのと両方ある感じ。
– 書類や記録を見る:誰にどんなケアをしたかのノートがちゃんとあるか。
– 現場を見る:スタッフが利用者さんとどう接しているか、安全に動けるかを直接見る。
– 聞き取りをする:利用者さんや家族、スタッフに話を聞いて問題がないか確かめる。
– 仕組みを見る:苦情の対応の仕方や職員の研修の仕組みが整っているか。
これを、事前に予定を伝えて行くこともあるし、突然行くこともあるよ。学校の保健の先生が来るときと、急に来て防災の様子をチェックするのと両方ある感じ。
アヤ: もしルールを守ってないところがあったら、どうなるの?
馬淵: まずは「ここを直してね」とやさしく教えることが多いよ。学校で言えば「黒板の書き方を直してね」と言うのと同じ。でももし何度言っても良くならなかったり、利用者さんが危なくなるような場合は、もっと強い対応をするんだ。たとえば改善計画を出させたり、サービスを止めさせたり、ひどければ指定を取り消してその事業所がそのサービスを続けられないようにすることもあるよ。これは利用者さんの命や安全を守るためなんだ。
アヤ: へえ、厳しいこともするんだね。監督する人たちは誰なの?
馬淵: 指定権者は普通、市役所や区役所の担当部署だよ。専門の人たちが書類をチェックしたり、看護師さんや介護の専門家と一緒に現場を見ることもある。外部の専門家に助けを借りることもあるんだ。学校で校長や保健の先生、外部の先生が来るのと似ているね。
アヤ: 最後に、ケアマネになったらアヤはどんなふうに関わるの?
馬淵: ケアマネは利用者さんの暮らしを守る大事な役目だよ。事業所がルールを守るように声をかけたり、利用者さんからの困りごとを指定権者に伝えたりすることもある。まるでクラスで困っている友だちを先生に相談する役目みたいなものだよ。何かあったらまた質問してね。
指定権者の指定取消しや指定停止の要件は何ですか?
アヤ: ケアマネになりたい女子小学生のアヤだよ!馬淵先生、指定権者の指定取消しや指定停止の要件は何ですか?教えて〜
馬淵: アヤさん、いい質問だね。まず「指定権者」は市や町などの役所のことだよ。介護サービスの事業者を「ここでサービスしていいよ」と指定する人たちなんだ。指定を「取消し」や「停止」するのは、その事業者がルールを守っていないときや利用者の安全が心配なときにする措置なんだよ。わかりやすく言うと、学校でルールを破ったクラブは先生に活動を止められたり、最悪クラブ自体をやめさせられたりするのと似ているよ。
馬淵: もう少し具体的に言うと、よくある要件はこんなものだよ。
– 虚偽の請求(やっていないことをやったとウソを書いてお金をもらう)や不正が見つかったとき。
– 利用者に危害を与えるような虐待や重大な事故があったとき。
– 資格や基準を満たさなくなってサービスを続けられないとき(例えば事業所が閉まったり、必要な人手が全くいなくなったり)。
– 何度もルール違反をして改善しないとき。
「停止」は一時的に活動を止めることで、「取消し」は指定を取り消してその事業所が介護保険サービスを提供できなくなることだよ。
– 虚偽の請求(やっていないことをやったとウソを書いてお金をもらう)や不正が見つかったとき。
– 利用者に危害を与えるような虐待や重大な事故があったとき。
– 資格や基準を満たさなくなってサービスを続けられないとき(例えば事業所が閉まったり、必要な人手が全くいなくなったり)。
– 何度もルール違反をして改善しないとき。
「停止」は一時的に活動を止めることで、「取消し」は指定を取り消してその事業所が介護保険サービスを提供できなくなることだよ。
アヤ: へえ、なんだか大変……もし停止とか取消しになったら利用者さんはどうなるの?
馬淵: 良い心配だね、アヤさん。役所は利用者さんの暮らしが急に困らないようにする義務があるんだ。具体的にはこうすることが多いよ。
– 別の事業者に引き継いだり、一時的に別のサービスを手配したりする。
– 緊急のときは直接対応して安全を確保する。
たとえば、いつも通っている学童が使えなくなったら、別の学童に行けるように手伝ってくれる感じだよ。ケアマネ(介護支援専門員)は利用者さんの生活が壊れないように調整する専門家だから、そういう場面で動くんだ。
– 別の事業者に引き継いだり、一時的に別のサービスを手配したりする。
– 緊急のときは直接対応して安全を確保する。
たとえば、いつも通っている学童が使えなくなったら、別の学童に行けるように手伝ってくれる感じだよ。ケアマネ(介護支援専門員)は利用者さんの生活が壊れないように調整する専門家だから、そういう場面で動くんだ。
アヤ: 事業者さんはどうしたら指定を守れるの?見張られてるのかな?
馬淵: 見張られているわけじゃなくて、みんなが安心してサービスを受けられるようにルールがあるんだよ。事業者が注意することはこんなことだよ。
– 請求や記録は正しくする(ウソを書かない)。
– 利用者さんの安全を最優先にして、事故や虐待が起きないようにする。
– スタッフの資格や人数、設備の基準を守る。
– 役所への報告や指示に素直に従い、問題があればすぐ直す。
たとえると、宿題を正しくやって先生に見せる、間違えたら素直に直して説明する、という感じ。誠実に対応すれば大きな処分にはなりにくいんだよ。
– 請求や記録は正しくする(ウソを書かない)。
– 利用者さんの安全を最優先にして、事故や虐待が起きないようにする。
– スタッフの資格や人数、設備の基準を守る。
– 役所への報告や指示に素直に従い、問題があればすぐ直す。
たとえると、宿題を正しくやって先生に見せる、間違えたら素直に直して説明する、という感じ。誠実に対応すれば大きな処分にはなりにくいんだよ。
アヤ: 具体的な悪い例を教えて!どんなことが一番ダメなの?
馬淵: 一番まずいのは利用者さんを傷つけることと、お金をだますことだね。例えば、
– 実際には行っていない訪問をしたと書いて報酬をもらう(虚偽請求)。
– 利用者さんに暴力を振るったり、必要な処置を放置してひどい結果にする(虐待や重大な提供ミス)。
こういうことが見つかると、重大な処分の対象になりやすいよ。逆に小さな手続きのミスならまず指導や改善命令で済むことが多いんだ。
– 実際には行っていない訪問をしたと書いて報酬をもらう(虚偽請求)。
– 利用者さんに暴力を振るったり、必要な処置を放置してひどい結果にする(虐待や重大な提供ミス)。
こういうことが見つかると、重大な処分の対象になりやすいよ。逆に小さな手続きのミスならまず指導や改善命令で済むことが多いんだ。
アヤ: なるほど〜。将来ケアマネになったら、利用者さんの安全を守ることが大事ってことだね。ありがとう!
馬淵: どういたしましてとは言えないけれど、安心して。アヤさんがその気持ちを持っていれば、利用者さんのことをよく考えられるケアマネになれるよ。何かほかに気になることがあったらまた聞いてね。
指定権者とサービス提供事業者の違いは何ですか?
アヤ: 馬淵先生!ケアマネになりたいアヤだよ!指定権者とサービス提供事業者の違いってなに?教えて!
馬淵: アヤさん、いい質問だね。かいごの学校の校長として、わかりやすく説明するよ。
簡単に言うと、指定権者はルールを作ったり「ここでサービスをやっていいよ」と許可を出す人たちで、サービス提供事業者は実際にサービスをする人たちだよ。
たとえばおまつりの例で考えてみよう。
– 指定権者は町役場の人で、「この場所で出店していいよ」とか「ルールを守ってね」と決める人。
– サービス提供事業者はお店を出す人たちで、来た人に食べ物を渡したり遊びを提供したりする人たち。
指定権者がいないと誰でも好き勝手にやってしまうから、安全やルールの管理がむずかしくなるんだ。
簡単に言うと、指定権者はルールを作ったり「ここでサービスをやっていいよ」と許可を出す人たちで、サービス提供事業者は実際にサービスをする人たちだよ。
たとえばおまつりの例で考えてみよう。
– 指定権者は町役場の人で、「この場所で出店していいよ」とか「ルールを守ってね」と決める人。
– サービス提供事業者はお店を出す人たちで、来た人に食べ物を渡したり遊びを提供したりする人たち。
指定権者がいないと誰でも好き勝手にやってしまうから、安全やルールの管理がむずかしくなるんだ。
アヤ: じゃあ、もしサービス提供事業者がルールを守らなかったらどうなるの?
馬淵: いい視点だね。そういうときは指定権者が注意したり、直させたり、それでもダメなら「許可を取り消す」こともあるんだよ。
おまつりで言うと、ゴミを片づけなかったり危ないことをした出店は、町役場が注意して閉めてもらうことがある、という感じだね。
それと、指定権者はサービスの質をチェックするために調査に来ることもあるよ。
おまつりで言うと、ゴミを片づけなかったり危ないことをした出店は、町役場が注意して閉めてもらうことがある、という感じだね。
それと、指定権者はサービスの質をチェックするために調査に来ることもあるよ。
アヤ: ケアマネは指定権者の人なの?それともサービス提供事業者の人?
馬淵: ケアマネはふつうサービス提供事業者の一員として働くことが多いよ。たとえば「居宅介護支援事業所」という事業所に所属して、利用者さんの相談にのったり、ケアプランを作ったりするんだ。
でもケアマネの仕事は、利用者さんとサービスをする人たち、そして市役所などの指定権者の間をつなぐ役目も持っている。だから、両方のことをよく知って調整するのが大事なんだよ。
でもケアマネの仕事は、利用者さんとサービスをする人たち、そして市役所などの指定権者の間をつなぐ役目も持っている。だから、両方のことをよく知って調整するのが大事なんだよ。
アヤ: なるほど〜!じゃあ最後にもう一回、短く教えて!
馬淵: うん。短くまとめるね。
– 指定権者:町や市がルールを決めて、サービスをやっていいか許可したり監督したりする人たち(役所の人)。
– サービス提供事業者:実際に介護サービスを利用者に提供するところや人たち(訪問ヘルパーやデイサービスなど)。
ケアマネはサービス提供の側にいることが多いけれど、両方の間をつなぐ大切な役割をするよ。どうかな、アヤさん、もう少し聞きたいことある?
– 指定権者:町や市がルールを決めて、サービスをやっていいか許可したり監督したりする人たち(役所の人)。
– サービス提供事業者:実際に介護サービスを利用者に提供するところや人たち(訪問ヘルパーやデイサービスなど)。
ケアマネはサービス提供の側にいることが多いけれど、両方の間をつなぐ大切な役割をするよ。どうかな、アヤさん、もう少し聞きたいことある?
指定権者が関わる契約や報酬の取り扱いはどうなっていますか?
アヤ: 馬淵先生、指定権者が関わる契約や報酬の取り扱いはどうなってるの?教えてー!
馬淵: アヤさん、それは大事なことだね。簡単に言うと、指定権者は「この人たちはお仕事していいよ」と許可を出す人で、実際の契約やお金のやり取りは基本的にサービスをする事業者と利用する人の間で行われます。たとえると、指定権者は遊園地の安全係で、遊具を使って遊ぶ人と遊具の管理者が直接やりとりする感じだよ。
アヤ: えーっと、利用する人がお金を払うの?それとも市とかが払うの?
馬淵: いい質問だね。実際は二つの部分があるんだ。サービスの代金は「保険から払われる分」と「利用者が自分で払う分(自己負担)」に分かれるよ。わかりやすく言うと、遊園地の乗り物の料金をチケット(保険)が一部払って、あと少しは自分のお小遣い(自己負担)で払うイメージ。請求や支払い手続きは事業者が市町村などに請求して、そこから保険分が支払われる仕組みなんだ。
アヤ: 指定権者が許可した人がおかしいことしたらどうなるの?たとえばお金を隠したりしたら…
馬淵: 指定権者はただの見守り役じゃなくて、ルールを守っているかチェックする役目もあるよ。たとえば、遊具の管理がずさんだったら遊園地の安全係が注意したり、ひどければ遊具を使わせないようにするでしょ。それと同じで、事業者がルールを破ったり不正をしたら、指定を取り消したり、正しい支払いに戻すように指示を出したりします。そして必要なら調査して徴収(返してもらう)することもあるんだ。
アヤ: じゃあ、契約書って誰と誰が書くの?市が書くの?
馬淵: 契約書は基本的にサービスを受ける人(利用者)と事業者が交わすよ。指定権者は「その事業者が契約していいですよ」と許可を出す立場だから、契約の中身が法律やルールに合っているか見たり、必要な情報を提供したりすることはあるけど、普段は当事者同士で書いていくんだ。これも、学校でいうと先生がルールを教えて見守るけど、友だち同士の約束は自分たちで決めるのと似ているね。
アヤ: 最後に、報酬の金額は誰が決めるの?事業者が勝手に高くしたりできるの?
馬淵: 報酬の大きな枠は国や関係機関が決めたルール(介護報酬のような決まり)で決まっているから、事業者が勝手に大きく変えることはできないよ。たとえば、給食のメニューと値段が学校で決まっているみたいに、基準があるんだ。その上で、利用者の状態に合わせた調整がされることはあるけど、全体の仕組みは監督する人たちがちゃんと見ているから安心していいよ。
アヤ: なるほど〜!指定権者は見張る人で、契約は利用者と事業者、報酬はルールで決まるんだね。もうちょっと質問してもいい?
馬淵: もちろんいいよ。どこがもっと知りたいかな?細かい手続きや、利用者の同意の取り方についてもやさしく説明するから、聞いてね。
利用者から見た指定権者の権利と保護はどうなっていますか?
アヤ: 馬淵先生!ケアマネになりたいんだけど、利用者から見た指定権者の権利と保護ってどんなものなの?教えてほしい!
馬淵: アヤさん、いい質問だね。指定権者という言葉はいろんな場面で使われるけど、ここでは「サービスを決めたり、頼んだりする人の権限」を想像して説明するね。たとえば指定権者は「お弁当を作る人を決める人」みたいなもの。利用者の立場から見ると、主に次のことが大事な権利と保護になるよ。
– 情報を受ける権利:どんなサービスを誰がどうやってやるのか、わかりやすく説明してもらう権利。お弁当の中身を全部教えてもらうみたいなものだよ。
– 同意する権利:勝手に決められず、納得してからサービスを受ける権利。嫌いなものを無理に入れられないのと同じだね。
– プライバシーの保護:個人の情報は必要な人だけに伝えられること。お手紙を大事に封筒で渡すように扱われるんだ。
– 苦情や変更を求める権利:合わないときは相談したり、別の人にしてもらうようお願いできる権利。先生に「交換して!」って言える感じ。
– 安全に守られること:虐待や不適切な扱いから守られる仕組みがあること。校内で安全ルールがあるのと似ているよ。
– 情報を受ける権利:どんなサービスを誰がどうやってやるのか、わかりやすく説明してもらう権利。お弁当の中身を全部教えてもらうみたいなものだよ。
– 同意する権利:勝手に決められず、納得してからサービスを受ける権利。嫌いなものを無理に入れられないのと同じだね。
– プライバシーの保護:個人の情報は必要な人だけに伝えられること。お手紙を大事に封筒で渡すように扱われるんだ。
– 苦情や変更を求める権利:合わないときは相談したり、別の人にしてもらうようお願いできる権利。先生に「交換して!」って言える感じ。
– 安全に守られること:虐待や不適切な扱いから守られる仕組みがあること。校内で安全ルールがあるのと似ているよ。
馬淵: また何か分からないことがあったら言ってね。次に、もし指定権者がよくないことをしたら利用者はどう対処できるか、説明しようか?
アヤ: うん!もし指定権者がだめなことをしたら、利用者さんはどんなふうに守られるの?
馬淵: いい追質問だね。利用者側の保護としては、実際にはこういう道があるよ。
– まず相談窓口に言う:担当のケアマネや施設の相談係、自治体の窓口に知らせることができる。クラスで困ったら先生に相談するのと同じ。
– サービスの停止や変更を申し出る:合わないサービスは止めたり、別の事業者に変えたりできることが多い。
– 第三者の調査や監査:市や都道府県が調べたり指導したりする仕組みがある。学校で問題があると保護者や教頭先生が介入するようなものだよ。
– 法的な手段:どうしても解決しないときは弁護士さんに相談することもある。これはもっと大きな相談にあたるね。
– まず相談窓口に言う:担当のケアマネや施設の相談係、自治体の窓口に知らせることができる。クラスで困ったら先生に相談するのと同じ。
– サービスの停止や変更を申し出る:合わないサービスは止めたり、別の事業者に変えたりできることが多い。
– 第三者の調査や監査:市や都道府県が調べたり指導したりする仕組みがある。学校で問題があると保護者や教頭先生が介入するようなものだよ。
– 法的な手段:どうしても解決しないときは弁護士さんに相談することもある。これはもっと大きな相談にあたるね。
馬淵: 次に、利用者さんが自分の意見や希望をどう伝えればいいか、わかるように教えるね。いいかな?
アヤ: うん!自分のことを伝えるのってちょっとむずかしそうだけど、教えて!
馬淵: 伝え方もいくつかあるよ。
– まずは話すこと:ケアマネやスタッフに「こうしてほしい」と具体的に伝える。例えば「朝は静かに起こしてほしい」と言う感じ。
– 家族や信頼できる人に一緒に来てもらう:伝えにくいときは味方に付いてもらうと安心だね。
– 書いて残す:希望や苦情をメモにしておくと、あとで記録として残るから伝えやすいよ。
– 定期的な見直しの場を使う:ケアプランの話し合いの場で、自分の思いを毎回伝えることができるよ。
– まずは話すこと:ケアマネやスタッフに「こうしてほしい」と具体的に伝える。例えば「朝は静かに起こしてほしい」と言う感じ。
– 家族や信頼できる人に一緒に来てもらう:伝えにくいときは味方に付いてもらうと安心だね。
– 書いて残す:希望や苦情をメモにしておくと、あとで記録として残るから伝えやすいよ。
– 定期的な見直しの場を使う:ケアプランの話し合いの場で、自分の思いを毎回伝えることができるよ。
馬淵: アヤさん、今日はいいところまで聞けたね。もっと知りたいことがあったらまた聞いてくれるかな。
指定権者が関与する個人情報保護のポイントは何ですか?
アヤ:ねえ馬淵先生!ケアマネになりたいアヤだよー!指定権者が関わる個人情報の守り方って、どんなところに気をつければいいの?
馬淵:かいごの学校の校長、馬淵です。いい質問だね、アヤさん。まず「指定権者」っていうのは、市や町みたいにサービスを決める立場の人たちのことだよ。ちょっと例えると、学校でルールを作る先生たちのようなもの。その先生たちが関わるときの個人情報のポイントは大きく分けていくつかあるんだ。
馬淵:ポイントをやさしく言うとこんな感じだよ。
– 使う目的をはっきりさせること:ノートに何を書くか決めてから書くみたいなもの。
– 必要な分だけ集めること:お弁当のおかずをみんなに配るとき、余分に渡さないで必要な人だけにする感じ。
– 触れる人を決めておくこと:宝箱の鍵を持つ人を限るイメージ。
– 安全にしまうこと:大事な手紙は鍵付きの箱や暗号で守ること。
– ルールを書いて約束すること:約束ごと(契約)を作って守ってもらう。
– 問題が起きたらすぐ対処すること:風船が破れたら空気を止めて片付けるように、漏れたら慌てず手順を踏むこと。
– 使う目的をはっきりさせること:ノートに何を書くか決めてから書くみたいなもの。
– 必要な分だけ集めること:お弁当のおかずをみんなに配るとき、余分に渡さないで必要な人だけにする感じ。
– 触れる人を決めておくこと:宝箱の鍵を持つ人を限るイメージ。
– 安全にしまうこと:大事な手紙は鍵付きの箱や暗号で守ること。
– ルールを書いて約束すること:約束ごと(契約)を作って守ってもらう。
– 問題が起きたらすぐ対処すること:風船が破れたら空気を止めて片付けるように、漏れたら慌てず手順を踏むこと。
アヤ:へー!鍵付きの宝箱みたいに守るんだね。じゃあ具体的にどうやって鍵をかけるの?パスワードとか?
馬淵:その通り、アヤさん。鍵のかけ方の例をもっとやさしく言うとこうなるよ。
– パスワードや暗号(データの暗号化)は鍵みたいなもの。強い鍵を作って他の人に教えない。
– 紙の書類は鍵のかかる引き出しに入れる。写真やノートも同じ。
– 誰が見たかを記録すること(アクセス履歴)は、図書カードみたいに「誰が借りたか」を残すこと。
– 指定権者が関わるときは、市や町が「こうしてください」というルール(通知や契約)を作って、サービス業者に守らせる。
– 人に渡すときは約束(同意)をもらってから。友達の秘密を話す前に「いい?」って聞くのと同じだよ。
– パスワードや暗号(データの暗号化)は鍵みたいなもの。強い鍵を作って他の人に教えない。
– 紙の書類は鍵のかかる引き出しに入れる。写真やノートも同じ。
– 誰が見たかを記録すること(アクセス履歴)は、図書カードみたいに「誰が借りたか」を残すこと。
– 指定権者が関わるときは、市や町が「こうしてください」というルール(通知や契約)を作って、サービス業者に守らせる。
– 人に渡すときは約束(同意)をもらってから。友達の秘密を話す前に「いい?」って聞くのと同じだよ。
アヤ:もし秘密が漏れちゃったらどうなるの?どう直すの?
馬淵:いい質問だね、アヤさん。漏れたときの対応はこう考えてね。
– まず漏れを止める:風船の穴をふさぐように、原因を探して止める。
– 被害を小さくする:今後同じことが起きないように追加の鍵をつけるなど対策する。
– 関係者に知らせる:本人や関係する機関に「こういうことが起きました」と伝える(ただし伝え方にも配慮がいる)。
– 記録を残して学ぶ:何が悪かったかノートに書いて、次に同じ間違いをしないようにする。
– ルールを変える必要があれば変える:新しい鍵を作ったり、係の人を増やしたりするよ。
– まず漏れを止める:風船の穴をふさぐように、原因を探して止める。
– 被害を小さくする:今後同じことが起きないように追加の鍵をつけるなど対策する。
– 関係者に知らせる:本人や関係する機関に「こういうことが起きました」と伝える(ただし伝え方にも配慮がいる)。
– 記録を残して学ぶ:何が悪かったかノートに書いて、次に同じ間違いをしないようにする。
– ルールを変える必要があれば変える:新しい鍵を作ったり、係の人を増やしたりするよ。
アヤ:アヤがケアマネになったら、すぐできることって何かな?
馬淵:アヤさんができることはこんなことだよ。
– 情報を扱うときは「これ、何のため?」と自分に聞くこと。
– 必要ない情報は集めない。メモは最小限にする。
– 書類は必ず鍵をかける、パスワードは人に教えない。
– 誰と共有するかを記録する。誰に渡したかノートをつける感覚で。
– 困ったら上の人(指定権者や先輩)に相談する。自分だけで抱えないこと。
– 学んで慣れること。ルールや手順を何度も練習すると自然にできるよ。
– 情報を扱うときは「これ、何のため?」と自分に聞くこと。
– 必要ない情報は集めない。メモは最小限にする。
– 書類は必ず鍵をかける、パスワードは人に教えない。
– 誰と共有するかを記録する。誰に渡したかノートをつける感覚で。
– 困ったら上の人(指定権者や先輩)に相談する。自分だけで抱えないこと。
– 学んで慣れること。ルールや手順を何度も練習すると自然にできるよ。
アヤ:うん!わかったよ、馬淵先生。もっといろいろ聞いてもいい?
馬淵:もちろんだよ、アヤさん。これからも気になることがあれば何でも聞いて。少しずつ覚えていけば、立派なケアマネになれるよ。
指定権者がケアプランやケアマネジメントに与える影響は何ですか?
アヤ: ケアマネになりたい女子小学生のアヤだよ!馬淵先生、指定権者ってケアプランやケアマネジメントにどんな影響をあたえるの?
馬淵: アヤさん、いい質問だね。かいごの学校の校長として簡単に説明するよ。指定権者は、その地域でどのサービスをしていいかを決める「ルールを作る人」みたいなものなんだ。たとえば、学校で考えると校長が教室のルールや先生を決めるでしょ。それと同じで、指定権者はサービスの種類、事業者の資格、守るべき基準や点検のやり方を決めるんだよ。だからケアプランを書くときに「利用できるサービス」「使える時間」「お金のルール」などに影響が出るんだ。
アヤ: 指定権者って具体的に誰のこと?市役所とか?
馬淵: そのとおり、主に市区町村や都道府県が指定権者になることが多いんだ。国が基本の法律やルールを作って、詳しい決まりや指定は自治体が行うイメージだよ。学校でいえば教育委員会や校長がそれぞれ役割を持っているのに似ているね。
アヤ: ケアプランを書いたら指定権者に「ダメ」って言われることあるの?
馬淵: うん、あるよ。でも大抵は個人を否定するためじゃなくて「制度のルールに合っていないから直してね」という意味なんだ。たとえば
– 制度で認められていないサービスを入れている
– 回数や時間が上限を超えている
– 利用者の安全や必要性が十分に説明されていない
といった理由で修正を求められることがあるよ。そのときはケアマネが家族やサービス事業者と相談して、どう直すかを考えて再提出するんだ。学校で宿題を先生に直されて、もっと説明を書き足すように言われるのと似ているね。
– 制度で認められていないサービスを入れている
– 回数や時間が上限を超えている
– 利用者の安全や必要性が十分に説明されていない
といった理由で修正を求められることがあるよ。そのときはケアマネが家族やサービス事業者と相談して、どう直すかを考えて再提出するんだ。学校で宿題を先生に直されて、もっと説明を書き足すように言われるのと似ているね。
アヤ: もし指定権者のルールが変わったら、ケアマネのやり方も変わるの?
馬淵: 変わることがあるよ。ルールが変わると、使えるサービスや基準、書き方の細かい決まりが変わるから、それに合わせてケアプランの作り方やチェックの仕方を変えないといけない。だから将来ケアマネになるなら、新しいルールをよく読んで、自治体の担当と話したり、事業者と連携したりする力が大事になるんだ。分かりやすく言えば、ゲームのルールが変わったら遊び方を変えるのと同じだよ。
アヤ: なるほど〜。アヤが将来ケアマネになったら、今どんなことを勉強したらいいかな?
馬淵: いい目標だね。まずは人と話す力、相手の気持ちを聞く力を大事にしてね。ルールや制度については基礎を少しずつ学べば大丈夫だから、身近な大人に制度のことを聞いたり、ニュースや本で用語を覚えていくといいよ。それから実際の現場を見て経験を積むと、指定権者のルールがどう現場に影響するかがよく分かるようになるよ。
指定権者が変更になった場合の手続きと注意点は何ですか?
アヤ:馬淵先生、ケアマネになりたいアヤなんだけど、指定権者が変更になった場合の手続きと注意点ってどうなるの?教えてほしい!
馬淵:アヤさん、いい質問だね。まず「指定権者」っていうのは、サービスをやっていいよって決める役所のことだよ。わかりやすくいうと、学校でいうと「この先生がクラスをやっていいよ」と校長先生が決めるようなものなんだ。変更があるときの手続きは、大きく分けて「知らせる」「引き継ぐ」「確認する」の三つだよ。
アヤ:知らせるって、誰に知らせるの?どうやって?
馬淵:利用者や家族、ケアマネやサービス事業所に文書やお知らせで伝えるんだよ。たとえば、クラスの担任が変わるときにお知らせが来るでしょ?あれと同じで、いつから変わるか、誰が新しい指定権者か、サービスに変わりがあるかを知らせるんだ。口で言うだけじゃなくて紙や書面で受け取ると安心だよ。
アヤ:引き継ぐって何を引き継ぐの?
馬淵:ケアプランや利用者の情報、連絡先、これまでの記録を新しいところに移すことだよ。たとえば、友だちにノートを貸すときに中身を全部見せて、「どこまで勉強したか」を教えるのと似ているよ。大切なのは、利用者や家族が「その情報を新しい指定権者に渡していいよ」と同意すること。ノートの中に書いてある秘密(個人情報)があるから、勝手に渡しちゃダメなんだ。
アヤ:同意って、紙にサインするのかな?それとも口でいいの?
馬淵:できれば書面での同意が安心だよ。口でも伝えられるけど、あとで「渡してもいいって言ったかな?」とならないように、書類に名前を書いてもらうのが普通だよ。ノートを渡すときに「いいよ」って書いてもらう感じだね。
アヤ:もしサービスが急に止まっちゃったらどうなるの?こわいよ。
馬淵:急に止まらないように配慮するのが基本だけど、もし危ないときは市役所の介護保険担当やケアマネにすぐ連絡してね。緊急で代わりのサービスを手配してくれることが多いよ。これも、担任が急に休んでも副担任が来るみたいに、利用者さんが困らないように続ける工夫がされるんだ。
アヤ:じゃあ、誰に最初に連絡すればいい?順番が知りたい!
馬淵:まずは今のケアマネ(または利用している事業所)に連絡してね。次に市区町村の介護保険課、必要なら新しい指定権者に問い合わせる。家族や本人にもすぐ伝えて、一緒にどうするか相談するのが大事だよ。流れは「今のケアマネ→市役所の介護窓口→新しい指定権者」って覚えておくといい。
アヤ:最後に、気をつけることを三つだけ教えて!
馬淵:いいよ、アヤさん。
1) お知らせはよく読むこと:いつ変わるか、内容に違いがないかをチェックしてね。通知は大事な地図みたいなものだよ。
2) 同意と個人情報の扱い:データを渡すときは書面で許可を出すこと。ノートの中身を勝手に見せないように。
3) 継続手配を確認すること:サービスが途切れないように、代わりの手続きや連絡先を確認しておくこと。もし不安ならすぐにケアマネや市役所に相談してね。
1) お知らせはよく読むこと:いつ変わるか、内容に違いがないかをチェックしてね。通知は大事な地図みたいなものだよ。
2) 同意と個人情報の扱い:データを渡すときは書面で許可を出すこと。ノートの中身を勝手に見せないように。
3) 継続手配を確認すること:サービスが途切れないように、代わりの手続きや連絡先を確認しておくこと。もし不安ならすぐにケアマネや市役所に相談してね。
アヤ:わかった!馬淵先生、たくさん教えてくれて助かった!ケアマネになる勉強、もっとしたいな!
馬淵:いい心がけだよ、アヤさん。何かまた疑問が出てきたら、いつでも聞いておいで。具体的な書類の見方や、家族への説明のしかたも一緒に練習しよう。
指定権者に関する苦情・紛争が起きたらどう対応すべきですか?
アヤ:馬淵先生!指定権者に関する苦情や紛争が起きたら、どうしたらいいの?こわいけどケアマネになりたいから教えて!
馬淵:アヤさん、いい質問だね。まずは落ち着いて、安全を守ることが一番大事だよ。たとえば遊び場で友だちがけんかしたら先生はまず止めて、安全を確かめるよね。ケアマネも同じで、まず「けがや危ないことがないか」を見て、必要ならすぐ助けを呼ぶんだ。
アヤ:それから何をするの?誰の味方をしたらいいかわからないよ。
馬淵:味方を決めるのではなく、中立(真ん中)で聞くことが大切だよ。サッカーの審判さんみたいに、どちらの話も順番に聞いて、事実をしっかりメモするんだ。あと、聞くときは相手の気持ちを受け止める言葉を使うといい。たとえば「びっくりしたね」「つらかったね」みたいにね。
アヤ:メモってどうやって書けばいいの?難しそう。
馬淵:簡単にでいいよ。いつ(日時)、どこで(場所)、何があったか(具体的な行動)、誰が関わったか、どう感じたかを書けばOK。ノートに書くのは、後で事実を確認するときの地図みたいなものだよ。消えないように日時を書いて、必要なら写真や資料も保存するんだ。
アヤ:それを見せるのは誰に見せるの?
馬淵:まずは自分の上司や事業所の責任者に報告するんだ。指定権者そのものが相手の場合は、外に相談できる窓口に伝えることもあるよ。たとえば市や町の福祉の相談窓口、第三者の苦情解決の相談所、専門家に仲介してもらうこともできる。大事なのは、秘密(プライバシー)を守って、必要な人だけに説明することだよ。
アヤ:どうやって話し合いを進めるの?こわがって言えない人もいるよね。
馬淵:そういう時は、やさしく話しかけること。例として使える言葉を教えるね。
– 相手(苦情を言う人)に:今のお気持ちをゆっくり聞かせてください。危ないところはないか確認しますね。
– 指定権者や職員に:どんな経緯でそうなったのか、説明していただけますか。今は事実を整理したいです。
話し合いは短く区切って、相手が疲れないように休憩を入れるといいよ。第三者(公平な人)をそばに置くと安心して話せることが多いんだ。
– 相手(苦情を言う人)に:今のお気持ちをゆっくり聞かせてください。危ないところはないか確認しますね。
– 指定権者や職員に:どんな経緯でそうなったのか、説明していただけますか。今は事実を整理したいです。
話し合いは短く区切って、相手が疲れないように休憩を入れるといいよ。第三者(公平な人)をそばに置くと安心して話せることが多いんだ。
アヤ:もしも相手が怒って暴れたら?
馬淵:安全第一だよ。すぐに距離を取って、必要なら他のスタッフや警察、救急に連絡する。無理に止めようとしないで、大人や専門家を呼ぶんだ。あらかじめ事業所で「危険時の対応ルール」を決めておくと安心だよ。
アヤ:最後に、ケアマネとして心がけることを教えて!
馬淵:うん、まとめるとこうだよ。
– 安全を最優先にする(危険ならすぐ助けを呼ぶ)
– 中立で両方の話を聞く(審判のように)
– 事実をメモして記録する(あとで役立つ地図)
– 必要な人に速やかに報告する(上司や相談窓口)
– 相手の気持ちを受け止める言葉を使う(やさしく話す)
– プライバシーを守る(不要に広めない)
– 解決が難しければ第三者に仲介してもらう
– 安全を最優先にする(危険ならすぐ助けを呼ぶ)
– 中立で両方の話を聞く(審判のように)
– 事実をメモして記録する(あとで役立つ地図)
– 必要な人に速やかに報告する(上司や相談窓口)
– 相手の気持ちを受け止める言葉を使う(やさしく話す)
– プライバシーを守る(不要に広めない)
– 解決が難しければ第三者に仲介してもらう
アヤさん、こうやって一つ一つ覚えていけば大丈夫だよ。何か他に気になることはあるかな?
指定権者と市区町村や都道府県との関係はどうなっていますか?
アヤ: 馬淵先生、指定権者と市区町村や都道府県って、どんな関係なの?ケアマネになったらそこって何をするのか知りたい!
馬淵: アヤさん、いい質問だね。簡単に言うと、指定権者は「この人たち(事業者)が介護サービスをしていいよ」と公式に認める役割の人や組織のことだよ。市区町村や都道府県がその指定を出したり、見回したりするんだ。イメージとしてはこう考えてみてね。町の市区町村は「クラスの先生」で、身近で一人ひとりの子(住民)をよく見る役。都道府県は「学校の校長先生」のような立場で、たくさんのクラスをまとめてルールを作ったり、大きな問題を手伝ったりするんだ。
アヤ: なるほど〜。じゃあケアマネは誰とよくやりとりするの?クラスの先生?校長先生?
馬淵: ケアマネは普段は市区町村とたくさんやりとりすることが多いよ。市区町村は要介護認定をしたり、介護保険の窓口になって利用者の手続きや支払いを管理するからね。でも、事業者の指定のルールや大きな監督は都道府県が関わることもあるよ。だからケアマネは市役所の人やサービスを提供する事業所、それから必要なら都道府県の担当とも連絡を取るようになるんだ。
アヤ: もし今使ってるサービスの会社が急にダメになっちゃったら、おじいちゃんおばあちゃんはどうなるの?アヤ、心配だよ!
馬淵: いい心配だね、アヤさん。万が一、事業所が指定を取り消されたり閉じたりしたときは、市区町村がまず利用者の暮らしが困らないように動くよ。ケアマネは代わりに別の事業所を探したり、一時的に別の支援を手配したりする。例えると、担任の先生が急に休んだときに、学校が代理の先生を用意して授業を続けるのと似ているよ。ケアマネはその調整役で、利用者が困らないように橋渡しをするんだ。
アヤ: 最後の質問!事業所が「指定して!」って言いたいとき、どこに頼むの?ケアマネはそのとき何をするの?
馬淵: 事業所が指定を受けたいときは、市区町村か都道府県に申請するよ。どちらに申請するかは事業の種類や規模で決まることが多いんだ。ケアマネは直接その申請を出すことは少ないけれど、現場の声を市役所に伝えたり、利用者のニーズを一緒に説明したりして、適切なサービスが増えるようにサポートする役割をするよ。簡単に言えば、ケアマネは利用者の立場で「こういうサービスが必要です」と行政に相談したり調整したりする係なんだ。
アヤ: ありがとうじゃなくて…お礼は言えないけど、なるほどって思った!もっと勉強してケアマネになりたい!
馬淵: アヤさん、その気持ちを大切にしてね。これからも気になることがあったら聞いておくれ。いつでも一緒に考えていこう。
指定権者に関する実務上よくあるミスとその対処法は何ですか?
アヤ:馬淵先生!ケアマネになりたいんだけど、指定権者って何?実務でよくあるミスとその対処法を元気に教えてほしい!
馬淵:アヤさん、いい質問だね。指定権者というのは、ざっくり言うと「このサービスを使わせていいよ」と決める役所の人たちのことだよ。学校でいうと、部活動の顧問の先生や校長先生が「この子は部に入っていいよ」と決める感じかな。実務でよくあるミスとその対処法を、やさしい例えを交えていくつか話すね。
1) 指定権者が誰かを間違える
– ミスの中身:手続きを出す相手が市役所なのか都道府県なのか、サービスごとに違うのに誤って送ってしまう。
– 例え:遠足の申込書を違う担任に渡しちゃう感じ。
– 対処法:まず管轄を確認するチェックリストを作る。自治体のHPや担当窓口に電話で「このサービスの指定権者はどちらですか?」と確認して、確認した日付を記録しておくと安心。
2) 更新や届出の期限を忘れる
– ミスの中身:指定の更新申請や変更届を期限内に出さず、指定が切れてしまう。
– 例え:図書カードの期限を過ぎてしまい本が借りられなくなるようなもの。
– 対処法:カレンダーや共有のリマインダーで期限を登録。社内で担当者と代替担当を決め、書類チェック表を前もって準備する。
3) 申請書類の記入漏れ・添付漏れ
– ミスの中身:必要書類が足りないために申請が差し戻される。
– 例え:遠足のお弁当箱にフォークを入れ忘れるみたいなもの。
– 対処法:提出前に必ず二人でダブルチェックするテンプレートを使う。提出時には控え(写し)を保管し、届出の受理印や受領メールを保存する。
4) 変更届の出し忘れ(事業所の住所や管理者変更など)
– ミスの中身:人が変わったり場所が変わったのに届け出ないと、情報の齟齬でトラブルに。
– 例え:引っ越して転校届を出さないで友だちに知らせないのと同じ。
– 対処法:人事や施設管理の変更が起きたら必ず「届出要否チェックリスト」を使って提出を行う仕組みを作る。社内連絡フローを明確に。
5) 指定条件(人員配置や研修など)を満たしていない
– ミスの中身:指定された基準を満たさないまま運営してしまい、改善命令や指定取消しのリスク。
– 例え:クラスの係の仕事をやらないと叱られるのと似ているよ。
– 対処法:定期的に自分たちで点検する「内部監査」を行い、基準に基づいたチェックリストで確認。必要なら早めに改善計画を作って指定権者に相談する。
6) 報告書や実績表の記載ミス
– ミスの中身:実績の数字や内容を間違えて報告し、過払い請求などの問題に発展する。
– 例え:テストの答えを写し間違えて点数が合わなくなる感じ。
– 対処法:毎月の実績は締め日ごとに複数人で突合(つきあわせ)をして確認。データのエビデンス(記録)を残す。
1) 指定権者が誰かを間違える
– ミスの中身:手続きを出す相手が市役所なのか都道府県なのか、サービスごとに違うのに誤って送ってしまう。
– 例え:遠足の申込書を違う担任に渡しちゃう感じ。
– 対処法:まず管轄を確認するチェックリストを作る。自治体のHPや担当窓口に電話で「このサービスの指定権者はどちらですか?」と確認して、確認した日付を記録しておくと安心。
2) 更新や届出の期限を忘れる
– ミスの中身:指定の更新申請や変更届を期限内に出さず、指定が切れてしまう。
– 例え:図書カードの期限を過ぎてしまい本が借りられなくなるようなもの。
– 対処法:カレンダーや共有のリマインダーで期限を登録。社内で担当者と代替担当を決め、書類チェック表を前もって準備する。
3) 申請書類の記入漏れ・添付漏れ
– ミスの中身:必要書類が足りないために申請が差し戻される。
– 例え:遠足のお弁当箱にフォークを入れ忘れるみたいなもの。
– 対処法:提出前に必ず二人でダブルチェックするテンプレートを使う。提出時には控え(写し)を保管し、届出の受理印や受領メールを保存する。
4) 変更届の出し忘れ(事業所の住所や管理者変更など)
– ミスの中身:人が変わったり場所が変わったのに届け出ないと、情報の齟齬でトラブルに。
– 例え:引っ越して転校届を出さないで友だちに知らせないのと同じ。
– 対処法:人事や施設管理の変更が起きたら必ず「届出要否チェックリスト」を使って提出を行う仕組みを作る。社内連絡フローを明確に。
5) 指定条件(人員配置や研修など)を満たしていない
– ミスの中身:指定された基準を満たさないまま運営してしまい、改善命令や指定取消しのリスク。
– 例え:クラスの係の仕事をやらないと叱られるのと似ているよ。
– 対処法:定期的に自分たちで点検する「内部監査」を行い、基準に基づいたチェックリストで確認。必要なら早めに改善計画を作って指定権者に相談する。
6) 報告書や実績表の記載ミス
– ミスの中身:実績の数字や内容を間違えて報告し、過払い請求などの問題に発展する。
– 例え:テストの答えを写し間違えて点数が合わなくなる感じ。
– 対処法:毎月の実績は締め日ごとに複数人で突合(つきあわせ)をして確認。データのエビデンス(記録)を残す。
アヤ:馬淵先生、書類を忘れそうでこわい!忘れないコツって何かある?
馬淵:アヤさん、いいね、その不安はみんな持っているよ。忘れないコツは「習慣」と「道具」を作ることだよ。
– 習慣:毎月のルーティンを決める(例:月初に届出と更新をチェックする日を設ける)。
– 道具:チェックリスト、カレンダー、提出用フォルダ、提出控えの専用ボックスを用意する。学校で毎朝連絡帳を確認するのと同じだよ。
– 最後の一手:提出前に「受理確認」を電話かメールで取っておくと安心。受理番号や担当者の名前をメモしておくと後で困らない。
– 習慣:毎月のルーティンを決める(例:月初に届出と更新をチェックする日を設ける)。
– 道具:チェックリスト、カレンダー、提出用フォルダ、提出控えの専用ボックスを用意する。学校で毎朝連絡帳を確認するのと同じだよ。
– 最後の一手:提出前に「受理確認」を電話かメールで取っておくと安心。受理番号や担当者の名前をメモしておくと後で困らない。
アヤ:もし指定を取り消されそうになったら、どうするの?怖いよ。
馬淵:心配しないで、そういう時の基本は落ち着いて「事実を整理して、すぐに動く」ことだよ。
– まず事実確認:指定権者からの通知文をよく読み、何が問題かを明確にする。通知は学校の注意書きを読むみたいに大事に扱うんだ。
– 相談と報告:社内で関係者を集めて原因をはっきりさせる。指定権者には連絡して、必要な改善内容や期限を聞く。
– 改善計画の提出:やることを小さく分けて計画にして、終わったら証拠をそろえて報告する。治すための「作戦メモ」を出すイメージだよ。
– 記録を残す:やりとりや対応の記録を残しておくと、後で説明するときに助けになる。
– まず事実確認:指定権者からの通知文をよく読み、何が問題かを明確にする。通知は学校の注意書きを読むみたいに大事に扱うんだ。
– 相談と報告:社内で関係者を集めて原因をはっきりさせる。指定権者には連絡して、必要な改善内容や期限を聞く。
– 改善計画の提出:やることを小さく分けて計画にして、終わったら証拠をそろえて報告する。治すための「作戦メモ」を出すイメージだよ。
– 記録を残す:やりとりや対応の記録を残しておくと、後で説明するときに助けになる。
アヤ:なるほど!最後に馬淵先生、アヤさんでもできそうなチェックリストのポイントを3つだけ教えて!
馬淵:いいね、3つだけだね。覚えやすいように簡単に。
1) 誰が何をいつやるかを書いた「担当表」を作る(名前と締切をはっきり)。
2) 提出前に「必要書類一覧」と「記入チェック」をする(二人で見る)。
3) 提出後は「受領記録」を残す(受理印やメール、担当者名・日付)。
1) 誰が何をいつやるかを書いた「担当表」を作る(名前と締切をはっきり)。
2) 提出前に「必要書類一覧」と「記入チェック」をする(二人で見る)。
3) 提出後は「受領記録」を残す(受理印やメール、担当者名・日付)。
アヤ:ありがとうって言っちゃダメだった!でもすごく分かった気がするよ、馬淵先生!
馬淵:アヤさん、その気持ちが大事だよ。分かったら今度は小さな実践をやってみて、ご質問があればまた聞いてね。
指定権者に関する代表的な事例や判例から学ぶポイントは何ですか?
アヤ:馬淵先生!ケアマネになりたい女子小学生だよ!指定権者ってどんなことをする人なの?代表的な事例や判例からどんなことを学べばいいか教えて!
馬淵:アヤさん、いい質問だね。指定権者というのは、たとえば市や県の先生みたいに「この介護サービスを公式に使っていいよ」と決める人のことなんだよ。学校でいうと、校長先生がどのクラブに教室を使わせるか決める感じかな。判例から学ぶ大事なことは、決め方が公平であること、理由をちゃんと説明すること、利用する人が困らないように配慮すること、という点だよ。
アヤ:へえ、校長先生みたいなんだね!判例ってどんな困ったことがあったときに出てくるの?
馬淵:いいね、具体的な話をするよ。よくある事例はこんなものだよ。
– ある事業者の指定を取り消したとき、利用者が突然サービスを受けられなくなったケース。裁判所は、取り消す前にきちんと手続き(説明や反論の機会)を取るべきだと判断することが多いんだ。学校で言うと、急にクラブを追い出して部員が困るのは良くない、という感じ。
– 指定を出すときに、特別な理由なく身内を優遇したり、公平でない基準で決めた場合、裁判で問題になることがあるよ。これはテストの点で好きな子だけ高くしてしまうのと似ているね。
– サービスの質が悪いとされる事業者を外す判断でも、 evidence(証拠)がはっきりしていないと認められないことが多い。つまり、ただ「なんとなくダメ」と言うのはダメなんだ。
– ある事業者の指定を取り消したとき、利用者が突然サービスを受けられなくなったケース。裁判所は、取り消す前にきちんと手続き(説明や反論の機会)を取るべきだと判断することが多いんだ。学校で言うと、急にクラブを追い出して部員が困るのは良くない、という感じ。
– 指定を出すときに、特別な理由なく身内を優遇したり、公平でない基準で決めた場合、裁判で問題になることがあるよ。これはテストの点で好きな子だけ高くしてしまうのと似ているね。
– サービスの質が悪いとされる事業者を外す判断でも、 evidence(証拠)がはっきりしていないと認められないことが多い。つまり、ただ「なんとなくダメ」と言うのはダメなんだ。
アヤ:なるほど〜。ケアマネはそういうときにどうしたらいいの?
馬淵:ケアマネは利用者のそばにいるから、とても大切な役目があるよ。例えると、アヤさんが部活のキャプテンで、部員が困ったら校長先生に話す人みたいなものだね。具体的には、
– 利用者がサービスを失わないよう、事前に代わりの手配や移行計画を考えること。
– 指定権者に対して事実を正しく伝えたり、利用者の声を上げること(書面で記録を残すと良い)。
– 事業者の問題があれば、改善を促すために具体的な証拠や記録を集めること。
こうすると、裁判になっても「こういう理由で心配しました」と説明しやすくなるよ。
– 利用者がサービスを失わないよう、事前に代わりの手配や移行計画を考えること。
– 指定権者に対して事実を正しく伝えたり、利用者の声を上げること(書面で記録を残すと良い)。
– 事業者の問題があれば、改善を促すために具体的な証拠や記録を集めること。
こうすると、裁判になっても「こういう理由で心配しました」と説明しやすくなるよ。
アヤ:記録を残すのって難しそう…どうやってやればいいの?
馬淵:簡単な方法を教えるね。ノートやパソコンに「日時・誰が・何をしたか・どう困ったか」を書くだけで十分役に立つよ。たとえば、訪問した日付、利用者の様子、事業者とのやり取りの内容をメモする。これは、あとで「こういうときにこうした」と説明するための写真や日記みたいなものだよ。
アヤ:判例から学ぶ大事なポイントをまとめてほしい!
馬淵:いいね、短くまとめるよ、アヤさん向けにやさしく。
– 公平さ:特別扱いはダメ。皆にルールをきちんと。
– 手続きの丁寧さ:取り消したり決めたりする前に説明と反論のチャンスを与えること。
– 利用者保護:利用者が急に困らないよう、移行や代替手段を考えること。
– 証拠を残すこと:問題があれば記録や写真で裏付けをしておくこと。
– 透明性と利害関係の回避:誰が決めたかがはっきりしていて、私情が入らないこと。
– 公平さ:特別扱いはダメ。皆にルールをきちんと。
– 手続きの丁寧さ:取り消したり決めたりする前に説明と反論のチャンスを与えること。
– 利用者保護:利用者が急に困らないよう、移行や代替手段を考えること。
– 証拠を残すこと:問題があれば記録や写真で裏付けをしておくこと。
– 透明性と利害関係の回避:誰が決めたかがはっきりしていて、私情が入らないこと。
アヤ:わかった!ケアマネになったら、利用者のことをちゃんと守れるようにメモとかもたくさんするね!
馬淵:それは素敵だよ、アヤさん。メモを習慣にして、利用者の声を大事にすれば、指定権者の判断が問題になっても落ち着いて対応できるからね。何か他に聞きたいことあるかな?
指定権者をチェックするための実務的な確認項目は何ですか?
アヤ: 馬淵先生、ケアマネになりたい小学生のアヤだよ!指定権者をチェックするために実務で見るものって何かな?教えてほしい!
馬淵: アヤさん、いい質問だね。指定権者をチェックするっていうのは、その事業所が市区町村から「ここでサービスしていいよ」って許可をちゃんと受けているか確かめることなんだ。お店が営業許可を持っているか見るのと似ているよ。実務的に見る主な項目を簡単にまとめるね。
– 指定証や許可証の有無:許可証はお店の営業許可証みたいなもの。原本か写しを見せてもらおう。
– 指定番号と有効期間:許可に書いてある番号やいつまで有効かを確認する。切れていないかを見るんだ。
– 指定範囲(どんなサービスが認められているか):何をやっていいかの範囲が決まっているから、提供サービスがその範囲内か照らし合わせる。
– 登録・設置者の情報(法人名や代表者):誰が運営しているか、名簿や登記情報と一致するかチェックする。
– 契約書や料金表:サービス契約書の内容や料金が公表されているか、書面が整っているかを見る。
– 保険・賠償体制:事故があったときの保険や責任の取り方が整っているか。
– 過去の点検・監査結果や苦情対応の記録:市の監査や指導の記録、苦情が多くないかを確認する。
– 人員配置と資格:ケアマネや介護職員の資格や配置、常勤・非常勤の状況。名簿や資格証の提示を求めることもできる。
– 施設の安全対策と感染症対策、非常時対応:避難経路や消毒などのルールがあるかどうか。
– 契約を結んでいる自治体の窓口での照会:市区町村に問い合わせて指定状況を直接確認する。
– 指定証や許可証の有無:許可証はお店の営業許可証みたいなもの。原本か写しを見せてもらおう。
– 指定番号と有効期間:許可に書いてある番号やいつまで有効かを確認する。切れていないかを見るんだ。
– 指定範囲(どんなサービスが認められているか):何をやっていいかの範囲が決まっているから、提供サービスがその範囲内か照らし合わせる。
– 登録・設置者の情報(法人名や代表者):誰が運営しているか、名簿や登記情報と一致するかチェックする。
– 契約書や料金表:サービス契約書の内容や料金が公表されているか、書面が整っているかを見る。
– 保険・賠償体制:事故があったときの保険や責任の取り方が整っているか。
– 過去の点検・監査結果や苦情対応の記録:市の監査や指導の記録、苦情が多くないかを確認する。
– 人員配置と資格:ケアマネや介護職員の資格や配置、常勤・非常勤の状況。名簿や資格証の提示を求めることもできる。
– 施設の安全対策と感染症対策、非常時対応:避難経路や消毒などのルールがあるかどうか。
– 契約を結んでいる自治体の窓口での照会:市区町村に問い合わせて指定状況を直接確認する。
アヤ: 馬淵先生、指定証ってどこで見られるの?事業所に行ったらすぐ見せてもらえるのかな?
馬淵: いいね、実際に見るのは大事だよ。事業所では壁に掲示していることが多いから、まず訪問時に「指定証を見せてください」って頼んでみよう。図書館のカードを見せてもらうみたいな感覚だよ。もし見せてもらえなければ、次の方法があるよ。
– 事業所に文書で請求する(写しをもらう)。
– 市区町村の福祉窓口や公式サイトで指定事業者一覧を確認する。
– 指定番号を教えてもらって、その番号で自治体に照会する。
見せてもらうときは、発行日や有効期限、事業所名が一致しているかも忘れずに見ようね。
– 事業所に文書で請求する(写しをもらう)。
– 市区町村の福祉窓口や公式サイトで指定事業者一覧を確認する。
– 指定番号を教えてもらって、その番号で自治体に照会する。
見せてもらうときは、発行日や有効期限、事業所名が一致しているかも忘れずに見ようね。
アヤ: スタッフの資格とか安全って、どんなふうにチェックするの?難しそう…
馬淵: 難しく感じるけど、チームの顔ぶれを見るみたいに考えるとやりやすいよ。ポイントはこうだよ。
– ケアマネや介護士の資格証の提示:資格は名札や証書で確認できることが多い。学校の卒業証書を見せてもらうような感じ。
– 勤務時間や配置の実態:夜や土日の対応が必要なら、その時間に人がいるか確認する。書類だけでなく実際の体制も聞いてみよう。
– 教育・研修の記録:スタッフが勉強しているか、定期研修があるかを確認する。チームが勉強会をしているか見るイメージ。
– 健康管理や感染対策:手洗いの仕組みや消毒剤、マスクなどのルールが整っているかを確認する。
– 緊急時の対応表や連絡先:もしものときにどうするか、連絡先や避難の流れが書かれているかを見る。
– ケアマネや介護士の資格証の提示:資格は名札や証書で確認できることが多い。学校の卒業証書を見せてもらうような感じ。
– 勤務時間や配置の実態:夜や土日の対応が必要なら、その時間に人がいるか確認する。書類だけでなく実際の体制も聞いてみよう。
– 教育・研修の記録:スタッフが勉強しているか、定期研修があるかを確認する。チームが勉強会をしているか見るイメージ。
– 健康管理や感染対策:手洗いの仕組みや消毒剤、マスクなどのルールが整っているかを確認する。
– 緊急時の対応表や連絡先:もしものときにどうするか、連絡先や避難の流れが書かれているかを見る。
アヤ: もし「なんか変だな」と思ったら、どこに相談すればいいの?
馬淵: 大事なところだね。変だなと感じたら早めに動くといいよ。相談先はこういうところだよ。
– まずは事業所の責任者に直接聞いてみる(説明を求める)。
– 市区町村の介護保険担当窓口に相談する:指定の有無や過去の指導歴を確認してもらえる。
– 県や市の苦情窓口や消費生活センターにも相談できる場合がある。
– 深刻な事故や不正が疑われるときは、自治体や関係機関に報告する。
あとは、見つけやすい「危ないサイン」も覚えておくといいよ。許可証がない、説明が曖昧、料金が不透明、苦情を隠しているように見える、同じ話が何度も変わる、などがあれば注意しよう。壊れたドアがある店には入るのをためらうのと同じ感覚だよ。
– まずは事業所の責任者に直接聞いてみる(説明を求める)。
– 市区町村の介護保険担当窓口に相談する:指定の有無や過去の指導歴を確認してもらえる。
– 県や市の苦情窓口や消費生活センターにも相談できる場合がある。
– 深刻な事故や不正が疑われるときは、自治体や関係機関に報告する。
あとは、見つけやすい「危ないサイン」も覚えておくといいよ。許可証がない、説明が曖昧、料金が不透明、苦情を隠しているように見える、同じ話が何度も変わる、などがあれば注意しよう。壊れたドアがある店には入るのをためらうのと同じ感覚だよ。
アヤ: 具体的なチェックリストがあったら便利なんだけど、簡単なチェック表を作ってくれる?
馬淵: もちろん。アヤさん向けに簡単なチェック項目を作るね。持って行って使えるような短いものにするよ。
– 指定証の有無(掲示/写し)__
– 指定番号・有効期限一致__
– 提供サービスの範囲一致__
– 運営者(法人名・代表)一致__
– 契約書・料金表がある__
– 保険・賠償の記載がある__
– 職員の資格表示・配置__
– 研修・教育の記録__
– 感染症対策・避難計画__
– 過去の苦情・監査記録の有無__
これで最初は十分だよ。もっと詳しい説明や、実際に事業所を見学するときの話もできるから、気になることがあったらまた聞いてね。
– 指定証の有無(掲示/写し)__
– 指定番号・有効期限一致__
– 提供サービスの範囲一致__
– 運営者(法人名・代表)一致__
– 契約書・料金表がある__
– 保険・賠償の記載がある__
– 職員の資格表示・配置__
– 研修・教育の記録__
– 感染症対策・避難計画__
– 過去の苦情・監査記録の有無__
これで最初は十分だよ。もっと詳しい説明や、実際に事業所を見学するときの話もできるから、気になることがあったらまた聞いてね。
指定権者に関する最近の法改正や今後の動向は何ですか?
アヤ: ケアマネになりたい女子小学生です!馬淵先生、指定権者って最近の法改正でどう変わってるの?これからどんな動きになるのか教えて!
馬淵: アヤさん、いい質問だね。まず「指定権者」っていうのは、市町村などが介護サービスの事業者を「ここで仕事していいよ」と許可する役目のことなんだ。学校でいうと、校長先生がクラブや先生を選ぶみたいなものだよ。
最近の流れは大きく分けて三つあるよ。
1) 監督やチェックが強くなっていること。安全や不正の目が厳しくなって、違うと判断されれば指定を止められる仕組みがよりはっきりしてきている。学校で言えば、ルール違反のときに注意や追放のルールがはっきりした感じ。
2) 情報の見える化・デジタル化。介護のデータを集める仕組み(LIFEなど)や、事業者の情報を公開するシステムが整えられて、誰がどんなサービスをしているかがわかりやすくなってきた。学校で言えば成績表や出席簿がデータで学校全体で共有されるイメージだよ。
3) 質の確保と人手不足への対応。小さな事業所の統合や働き方改善の支援など、良いサービスを続けられるような仕組み作りが進んでいるよ。
これからは、もっとデータを使った監視や支援、透明性の向上、地域での役割分担が進むと見込まれているんだ。
最近の流れは大きく分けて三つあるよ。
1) 監督やチェックが強くなっていること。安全や不正の目が厳しくなって、違うと判断されれば指定を止められる仕組みがよりはっきりしてきている。学校で言えば、ルール違反のときに注意や追放のルールがはっきりした感じ。
2) 情報の見える化・デジタル化。介護のデータを集める仕組み(LIFEなど)や、事業者の情報を公開するシステムが整えられて、誰がどんなサービスをしているかがわかりやすくなってきた。学校で言えば成績表や出席簿がデータで学校全体で共有されるイメージだよ。
3) 質の確保と人手不足への対応。小さな事業所の統合や働き方改善の支援など、良いサービスを続けられるような仕組み作りが進んでいるよ。
これからは、もっとデータを使った監視や支援、透明性の向上、地域での役割分担が進むと見込まれているんだ。
アヤ: 指定取り消しって本当にあるの?どんなときにそんなことになるの?馬淵先生教えて!
馬淵: なることはあるよ、アヤさん。学校で言えば、みんなの安全を脅かしたり、ずるをしたり、約束を全然守らない先生やクラブがいると、校長が「もうここではできない」と決めることがあるでしょ。それと同じで、介護の世界でも例えばこんな場合に指定が取り消されたり注意されたりするんだ。
– 利用者の命や安全にかかわる重大なミスや放置があったとき(安全面の重大な問題)
– 介護報酬の不正請求などで嘘をついてお金を多く受け取っていたとき(ルール違反や不正)
– 指導や改善命令に従わず、何度も同じ問題を起こしたとき(改善しない場合)
実際にはまず注意や改善指導があって、それでも直らなければ指定をやめる、という段階を踏むことが多いよ。だから普段から約束を守ることが大事だね。
– 利用者の命や安全にかかわる重大なミスや放置があったとき(安全面の重大な問題)
– 介護報酬の不正請求などで嘘をついてお金を多く受け取っていたとき(ルール違反や不正)
– 指導や改善命令に従わず、何度も同じ問題を起こしたとき(改善しない場合)
実際にはまず注意や改善指導があって、それでも直らなければ指定をやめる、という段階を踏むことが多いよ。だから普段から約束を守ることが大事だね。
アヤ: ケアマネになったら、指定権者とどう仲良くしたらいいの?気をつけることを教えてほしい!
馬淵: 良い質問だね、アヤさん。ケアマネとしては、指定権者(市町村)との良い関係がとても大切だよ。ポイントを簡単に言うね。
– ルールを守ること:書類や報告をちゃんと出す、決められた手続きを守ることは学校の提出物と同じで基本だよ。
– 透明にすること:誰にどんなサービスを紹介したか、報酬のことなどをはっきりさせる。自分の家族や関係先を優先して紹介しない、という「利害関係の回避」を心がけてね。これは友だちとの公平さと同じだよ。
– 記録を丁寧につけること:相談や対応の記録は、あとで説明するときの大事な証拠になる。ノートにメモを残す習慣みたいなものだよ。
– データや新しい仕組みに慣れること:LIFEなどのシステムを使って、利用者の状態や効果を見える化する流れがあるから、ICTに慣れておくと役に立つよ。
– 地域と連携すること:医療やヘルパー、ケアマネ同士で情報を共有して、チームで支えると利用者にとって安心だよ。学校のイベントでみんなで協力するのと同じだね。
もっと聞きたいことがあれば、どんどん質問してね。アヤさんの好奇心はとても大事だから、続けて学んでいこう。
– ルールを守ること:書類や報告をちゃんと出す、決められた手続きを守ることは学校の提出物と同じで基本だよ。
– 透明にすること:誰にどんなサービスを紹介したか、報酬のことなどをはっきりさせる。自分の家族や関係先を優先して紹介しない、という「利害関係の回避」を心がけてね。これは友だちとの公平さと同じだよ。
– 記録を丁寧につけること:相談や対応の記録は、あとで説明するときの大事な証拠になる。ノートにメモを残す習慣みたいなものだよ。
– データや新しい仕組みに慣れること:LIFEなどのシステムを使って、利用者の状態や効果を見える化する流れがあるから、ICTに慣れておくと役に立つよ。
– 地域と連携すること:医療やヘルパー、ケアマネ同士で情報を共有して、チームで支えると利用者にとって安心だよ。学校のイベントでみんなで協力するのと同じだね。
もっと聞きたいことがあれば、どんどん質問してね。アヤさんの好奇心はとても大事だから、続けて学んでいこう。