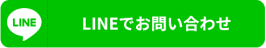ケアマネジャーって国家資格?ケアマネの目指し方や将来性について
 「ケアマネジャーはどんな資格なの?」
「ケアマネジャーはどんな資格なの?」
「ケアマネジャーを目指したいけど、需要はある?」
など疑問を抱いている方もいるでしょう。
この記事では、ケアマネジャーの概要について解説します。
ケアマネジャーの目指し方や将来性についても紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
ケアマネジャーとは
ケアマネジャーとは、介護を必要とする人々が、適切な介護保険サービスを利用できるよう支援する介護の専門職です。
「ケアマネジャー」や「ケアマネ」と呼ばれることもありますが、正式名称は「介護支援専門員」となっています。
ケアマネジャーは国家資格?

結論から言うと、ケアマネジャーは国家資格ではありません。
ケアマネジャーの正式名称である「介護支援専門員」は、各都道府県が認定している公的資格です。
ちなみに、介護系の資格で国家資格なのは「介護福祉士」のみです。
ケアマネジャー試験を受ける条件の一つに、介護福祉士業務を一定期間経験していることが含まれています。
今後、ケアマネジャーは国家資格化する?
現在のところ、ケアマネジャーを国家資格化する予定はありません。
しかし、2003年に政府が閣議決定した答弁書の中で、介護支援専門員資格が「国家資格」であると記載されていたことがありました。
どのような経緯で記載されていたかは分かっていません。
ただし、政府はケアマネジャーを国家資格と同等の専門性がある職種だと認めていたことが推測できます。
ケアマネジャーの仕事内容

ここからは、ケアマネジャーの仕事内容を解説します。
これからケアマネジャーを目指している方は、ぜひ参考にしてください。
- ケアプランの作成・給付管理
- サービス事業者との連携・調整
- 利用者やその家族からの介護相談
- 要介護認定の申請代行・聞き取り調査
ケアプランの作成・給付管理
ケアマネジャーの主な仕事内容は、利用者一人ひとりに適したケアプランの作成です。
ケアプランの作成は、利用者の身体状況や生活環境、希望、家族の状況などを総合的に評価することから始まります。
この評価から得られた情報を使い、利用者の自立支援と生活の質の向上を目指した具体的な目標を設定するのです。
次に、これらの目標を達成するために必要な介護サービスを選び、サービスの種類や頻度、提供事業者などを決定します。
この際、利用者の要介護度に応じた介護保険の給付限度額内でサービスを組み立てなければなりません。
ケアマネジャーが作成したケアプランは、利用者や家族に説明し、同意を得た上で実施されます。
また、ケアプランの作成後も定期的なモニタリングを実施し、必要に応じて見直しする必要があるのです。
介護保険サービスはもちろん、地域の社会資源や医療サービスなども適切に組み込み、包括的な支援をする必要があります。
サービス事業者との連携・調整
ケアマネジャーは、ケアプランに基づいて選定されたサービス事業者と連携・調整業務もします。
まず、利用者の状況やケアプランの内容を各サービス事業者に分かりやすく説明し、具体的なサービス内容を依頼していくのです。
この際、利用者の個別ニーズや注意点を明確に伝え、適切なサービス提供につなげなければなりません。
サービス開始後は、定期的に事業者からの報告を受け、サービスが計画通りに提供されているか、また利用者の状態に変化はないかを確認します。
もし、問題や課題が発生した場合は、関係者間で速やかな情報共有を行い、解決策を検討するのです。
他にも、サービス担当者会議を定期的に開催し、各事業者間の情報共有や方針の統一を図るのも重要な業務です。
これにより、質の高い一貫性のあるケアを提供し、利用者の「生活の質の向上」を目指します。
利用者やその家族からの介護相談
利用者やその家族からの介護相談も、ケアマネジャーの仕事内容となっています。
相談内容は、具体的な介護方法のアドバイスや利用可能なサービスの紹介など様々です。
初回相談時には、現在の利用者の状況や家族が困っていることを丁寧に聞き取り、介護保険制度の仕組みや利用できるサービスなどを紹介します。
他にも、必要に応じて介護に関する知識や技術などを、利用者やその家族へ伝えるのが仕事です。
もし、利用者家族の介護負担が大きい場合は、レスパイトケアの提案や、家族自身の健康管理の重要性について説明します。
また、利用者が認知症の場合は、症状の理解や適切な対応方法について詳しく説明し、家族の不安をできるだけ軽減するのが重要です。
経済的な問題がある場合は、利用可能な社会保障制度や地域の支援サービスについて情報提供します。
このように継続的な相談支援を通して、利用者やその家族との信頼関係を構築し、長期的な視点でケアマネジメントするのが、ケアマネジャーの仕事です。
要介護認定の申請代行・聞き取り調査
要介護認定の申請代行や聞き取り調査の支援も、ケアマネジャーの仕事の一つです。
新規の利用者や更新時期を迎えた利用者に対して、要介護認定の申請の必要性を説明し、手続きの流れを分かりやすく紹介します。
申請代行は、必要書類の準備をサポートし、利用者の代わりに市区町村の窓口へ必要書類を提出するのです。
この際、利用者の状況を正確に伝えるため、医療情報や日常生活の状況などを事前に確認しておかなければなりません。
また、認定調査員による聞き取り調査の際には、ケアマネジャーが利用者やその家族に同席することがあります。
調査前に、利用者の状況を家族と再確認し、普段の様子を漏れなく伝えられるよう準備するのが重要です。
介護認定の結果が出た後は、その内容を利用者やその家族に分かりやすく説明し、必要に応じて不服申し立ての手続きについても情報提供します。
要介護度に変更があった際は、新しい要介護度に応じたサービスの利用について説明し、ケアプランの見直しをしていくのです。
介護職員とケアマネジャーの違い
介護職員は、利用者に対し実際に介護するのが仕事です。
一方、ケアマネジャーは、実際に介護はせず、介護を必要とする人々が、適切な介護保険サービスを利用できるよう支援するのが仕事となっています。
介護職員は、ケアマネジャーが作成したケアプランをもとに介護するため、お互いを尊重し協働することが大切です。
ケアマネジャーの目指し方

続いて、ケアマネジャーの目指し方を解説します。
ケアマネジャーになるためには、ケアマネジャー試験を受けなければなりません。
ケアマネジャー試験の概要
ケアマネジャー試験の正式名称は、「介護支援専門員実務研修試験」です。
ほとんどの都道府県で5肢複択のマークシート方式が採用されており、試験時間は120分となっています。
ただし身体に障がいがあるなど特別な理由がある場合は、受験時間が別途定められています。
| 試験日 | 10月の第2日曜日 |
| 受験要項配布時期 | 5月~7月頃 ※各都道府県により異なる |
| 申込受付期間 | 各都道府県によって異なる |
| 合格発表日 | 12月上旬 |
| 合格率 | 2018年度(第21回)10.1% 2019年度(第22回)19.5% 2020年度(第23回)17.7% 2021年度(第24回)23.3% 2022年度(第25回)19.0% 2023年度(第26回)21.0% |
ケアマネジャー試験の応募資格
ケアマネジャー試験を受けるためには、以下①②のいずれかの条件を満たす必要があります。
①
| 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士含む)、精神保健福祉士のいずれかを保有し、これらの国家資格に基づく業務の実務経験が通算5年以上で、従事した日数が900日以上である。 |
②
| 生活相談員、支援相談員、相談支援専門員、主任相談支援員として、受験資格に定められる相談援助業務に通算5年以上の従事期間があり、従事した日数が900日以上である。 |
無資格からケアマネジャー資格取得までの流れ
無資格からケアマネジャー資格取得までの流れは、以下の通りです。
- 介護職員初任者研修を受講する
- 実務者研修を受講する
- 実務経験を積み、ケアマネジャー資格試験の受験資格を得る
- 必要書類を用意し、受験申し込みをする
- 「介護支援専門員実務研修受講試験」に合格する
- 合計87時間の「介護支援専門員実務研修」を受講する
- 研修修了後、3ヶ月以内に「介護支援専門員資格登録簿」へ登録申請する
- 「介護支援専門員証」の交付を申請する
介護支援専門員証の有効期限は5年のため、更新するのを忘れないようにしましょう。
ケアマネジャーの将来性はある

ケアマネジャーの将来性はあるので、これからケアマネジャーを目指す方は安心してください。
将来性があると断言できる理由として、以下の3つが挙げられます。
- 高齢化社会になり需要が拡大
- 介護の仕事はAIに代替されない
- ケアマネジャーの平均年齢が高い
高齢化社会になり需要が拡大
ケアマネジャーに将来性がある理由1つ目は、日本が高齢化社会になっており、介護需要が拡大しているからです。
日本の高齢化率は、2025年には約30%、2055年には約40%に達すると予想されています。
高齢者の割合が増え、介護を必要とする人が増えるため、今後もケアマネジャーの仕事はなくならないでしょう。
介護の仕事はAIに代替されない
2つ目の理由は、介護の仕事はAIに代替されないからです。
ケアマネジャー試験の合格率は低く、介護の専門性が非常に高い職種と言えます。
たしかに、AIはケアプランの作成などができるかもしれません。
しかし、これはあくまでも補助的なものにすぎず、最終的にはケアマネジャーが利用者にとって最適なケアプランを作成する必要があります。
利用者が安心して生活を送るためには、ケアマネジャーが必要不可欠なのです。
ケアマネジャーの平均年齢が高い
3つ目の理由は、ケアマネジャーの平均年齢が高いことが挙げられます。
介護労働安定センターが公表した「介護労働実態調査」によると、ケアマネジャーの平均年齢は53.6歳です。
また、60歳以上のケアマネジャーは全体の29.4%を占めており、今後10年以内に引退を考えるでしょう。
一方、40歳未満のケアマネジャーは、わずか7.6%しかいません。
介護事業所は、ケアマネジャー不足を解消するため、若い世代の採用を強化しています。
そのため、今後もケアマネジャーの需要はなくならないというわけです。
まとめ
ケアマネジャーの概要や目指し方、将来性について解説しました。
ケアマネジャーの正式名称は「介護支援専門員」で、国家資格ではなく公的資格です。
ケアマネジャーになるためには、実務経験を積み、難関のケアマネジャー試験に合格しなければなりません。
ただし、ケアマネジャーの需要は高く、将来性があるためケアマネジャー資格を取得しておいて損はないでしょう。
興味がある方は、ぜひケアマネジャー資格を取得してみませんか?