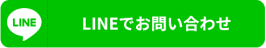ケアマネ試験の対策法を徹底解説!合格への近道と通信講座の活用法
目次
ケアマネ試験の対策法を徹底解説!合格への近道と通信講座の活用法
はじめに
ケアマネ試験に挑戦しようと決意したものの、「何から手をつければいいか分からない」「働きながら勉強時間を確保できるか不安」など、最初の一歩でつまずく人は少なくありません。
また、独学での勉強に限界を感じたり、効率的な学習方法を探したりしているうちに、時間ばかりが過ぎてしまうケースも多く見受けられます。
ケアマネ試験は、合格率15~20%程度の難関試験です。
単なる丸暗記では太刀打ちできず、正しい知識を体系的に身につけ、出題傾向を押さえた対策が不可欠となります。
特に、介護や医療の現場で働きながら受験を目指す方にとっては、限られた時間をいかに効率よく使うかが合否を分けるカギになります。
そんな中、近年注目を集めているのが「通信講座」の活用です。
特に人気講師・馬淵敦士先生による講座は、初心者でも無理なくステップアップできるカリキュラム設計と、徹底したサポート体制で、受講生から高い支持を集めています。
本記事では、次のような方に向けて、
-
ケアマネ試験に最短で合格したい方
-
忙しい中でも効率的に勉強を進めたい方
-
通信講座をうまく活用したい方
に向けて、「ケアマネ試験に合格するための具体的な対策法」を徹底解説していきます。
試験概要の基本情報から、独学と通信講座の違い、通信講座の選び方、さらには合格を引き寄せる学習計画の立て方まで、実践的なノウハウを網羅的にお伝えします。
ぜひ最後まで読み進めて、あなたの合格への道筋を明確にしてください!
第1章:ケアマネ試験の基本情報と合格への全体像
ケアマネ試験に取り組むうえで、まずは試験の概要と、どのように全体像を捉えて勉強を進めるべきかを理解しておくことが大切です。
ここでは、試験の基礎知識を押さえたうえで、合格への道筋を整理していきましょう。
■ ケアマネ試験とは?
ケアマネ試験(正式名称:介護支援専門員実務研修受講試験)は、介護支援専門員(ケアマネジャー)になるために必要な国家試験です。
介護保険制度の中核を担うケアマネは、介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、利用者とサービス提供事業者をつなぐ重要な役割を果たします。
このため、試験内容は単なる知識だけではなく、実践に即した総合的な判断力も問われる点が特徴です。
■ 出題形式と試験範囲
試験は以下の2分野から出題されます。
| 分野 | 問題数 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 介護支援分野 | 25問 | ケアマネジメントの基礎、介護保険制度、支援技術など |
| 保健医療福祉サービス分野 | 35問 | 医療知識、福祉制度、介護サービスの種類や内容など |
全60問・五肢複択方式(1問につき5つの選択肢から正解を選ぶ形式)で行われ、試験時間は120分です。
特に注意すべきポイントは、分野ごとの合格基準が設定されていること。
一般的には各分野で70%以上(介護支援分野は25問中18問、保健医療福祉サービス分野は35問中24〜25問程度)正解する必要があると言われています。
■ 合格までの全体戦略
ケアマネ試験に合格するためには、単に勉強を頑張るだけでは不十分です。
「合格までの全体像」を意識して、戦略的に学習を進めることが不可欠です。
-
出題傾向を把握する(→ケアマネ試験の合格率を上げる学習プランを参考に)
-
出やすい分野・テーマから優先的に学習する
-
過去問演習と復習をセットで繰り返す
-
模試で本番力を鍛える
-
直前期には“覚えるべきポイント”を徹底整理する
このような流れで勉強を進めれば、無理なく着実に合格力を高めることができます。
■ 通信講座を活用すれば「学びの地図」が手に入る
独学では、これらの全体戦略を自分で立てなければなりませんが、馬淵敦士先生の通信講座のような講座を活用すれば、
-
出題傾向に即したカリキュラム
-
優先順位に沿った学習スケジュール
-
適切なタイミングでの模試実施
といった「合格までの地図」が最初から用意されています。
これに沿って進めることで、無駄な回り道をせず、効率よくゴールを目指すことができるのです。
第2章:独学の限界と通信講座のメリット
ケアマネ試験に挑戦する際、多くの方が最初に悩むのが「独学でいけるのか?」「通信講座を使ったほうがいいのか?」という選択です。
もちろん、独学で合格を果たす方もいますが、限られた時間と労力を考えると、通信講座を活用したほうが圧倒的にコストパフォーマンスが高いといえます。
ここでは、独学と通信講座、それぞれの特徴を比較しながら、なぜ通信講座が多くの受験生に支持されているのかを解説していきます。
■ 独学のメリットと限界
独学の最大のメリットは、コストが抑えられることです。
市販のテキストや問題集を購入すれば、数千円〜1万円程度で学習環境を整えることができます。
しかし、独学には次のような限界もあります。
-
出題範囲が広く、重要ポイントを絞れない
-
学習ペースが自己管理になるため挫折しやすい
-
自己流の勉強では「理解不足」に気づきにくい
-
疑問点を解消できず、モヤモヤを抱えたまま進みやすい
特にケアマネ試験は、単なる暗記だけでなく、介護・医療・福祉の幅広い知識とその応用力が求められます。
このため、独学では「時間がかかりすぎる」「効率が悪い」という問題に直面しやすいのです。
■ 通信講座を活用するメリット
一方、通信講座には次のような強みがあります。
-
学習すべきポイントが最初から整理されている
-
講師によるわかりやすい解説で理解が深まる
-
質問サポートで疑問をすぐ解消できる
-
模試や演習問題で実力を測りながら進められる
-
学習スケジュールが提示されており、挫折しにくい
たとえば、馬淵敦士先生の通信講座では、重要ポイントを厳選したうえで、
-
動画講義
-
テキスト連動解説
-
模擬試験&解説
-
質問サポート
までトータルで提供されています。
つまり、何を・いつ・どのように学習すればよいかが最初から見えているため、最短ルートで合格に向かうことができるのです。
■ コスパの視点から考えると?
「通信講座は高い」と感じる方もいるかもしれません。
しかし、考えてみてください。
-
独学で勉強が非効率になり、再受験すれば追加で受験料・時間・精神的負担がかかる
-
通信講座を使えば、最短で合格でき、結果的に総コストが抑えられる
このように考えると、確実に結果を出すための自己投資として、通信講座の利用は非常に合理的な選択肢だといえます。
👉 独学に限界を感じたら:
ケアマネ学習法の詳しい解説はこちら
第3章:通信講座を選ぶ際のポイントとは?
通信講座を活用することで、ケアマネ試験合格への道がぐっと近づくことは間違いありません。
しかし、数多くの通信講座が存在する中で、どれを選べば良いのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか?
ここでは、失敗しない通信講座選びのポイントをわかりやすく解説します。
■ ① カリキュラムのわかりやすさ
まずチェックすべきは、「カリキュラムが体系的に整理されているか」です。
-
出題範囲を網羅しているか
-
重要ポイントを優先的に学べるか
-
無駄な学習を削減しているか
これらがしっかり設計されていない講座だと、時間がムダになったり、結局独学と変わらない状態になったりするリスクがあります。
たとえば、馬淵敦士先生の講座では、出題頻度の高いテーマを優先して学べるカリキュラムが組まれており、効率的に合格力を養成できます。
■ ② 講師の質とサポート体制
誰が教えてくれるか、そしてどんなサポートがあるかも非常に重要なポイントです。
-
豊富な指導経験があるか
-
ケアマネ試験に精通しているか
-
質問対応がスムーズか
特に、質問に対するレスポンスが遅い講座は、疑問を抱えたまま学習を進めることになり、モチベーションの低下にもつながりかねません。
馬淵敦士先生の講座では、わからない箇所を無制限で質問できるため、安心して学習を進めることができます。
■ ③ 受講生の合格実績をチェック
講座を選ぶ際には、実際にその講座を受講した人たちがどのくらい合格しているか、合格実績にも注目しましょう。
-
合格者の声や体験談が掲載されているか
-
合格率に関するデータが公開されているか
実績のある講座は、やはりノウハウの蓄積があり、受験生の気持ちに寄り添った指導ができるものです。
■ ④ スキマ時間活用に向いているか?
現代人にとって、机に向かって何時間も勉強するのは現実的ではありません。
スマホやタブレットで講義動画が視聴できるか、短時間で学習できるコンテンツ設計になっているかも、重要なチェックポイントです。
-
動画講義がスマホ対応しているか
-
1本あたりの動画が短時間で区切られているか
これにより、通勤・休憩時間など、スキマ時間を最大限に活用することが可能になります。
■ あなたに合った講座を見つけよう
通信講座を選ぶ際は、「人気があるから」ではなく、
自分の学習スタイルに合うかどうかを重視しましょう。
特に、
-
忙しくても効率的に学びたい
-
確実に合格したい
-
信頼できる講師から学びたい
という方には、馬淵敦士先生のケアマネ受験対策講座をおすすめします。
👉 合格への第一歩を踏み出すなら:
ケアマネ受験準備についてはこちら
第4章:馬淵敦士先生の講座で合格を目指す!
ケアマネ試験合格を目指すにあたって、数ある通信講座の中でも特に注目されているのが、馬淵敦士先生によるケアマネ受験対策講座です。
この章では、なぜ馬淵先生の講座が多くの受験生に選ばれているのか、その具体的な特徴と魅力を詳しくご紹介します。
■ 馬淵敦士先生とは?
馬淵敦士先生は、ケアマネ試験対策において多数の合格者を輩出してきた実力派講師です。
長年にわたり試験対策の指導を行ってきた経験を活かし、受験生のつまずきやすいポイントを徹底的に分析。
そのうえで、「必要な知識だけを、わかりやすく、最短ルートで身につける」ことを重視した講義を展開しています。
また、人気書籍
-
『この1冊で合格! 馬淵敦士のケアマネ テキスト&問題集 2025年度版』
-
『ゼロからスタート! 馬淵敦士のケアマネ1冊目の教科書 2025年度版』
の著者でもあり、本当に使える教材と、講義との完全連動が高く評価されています。
■ 馬淵敦士先生の講座の特徴
【特徴1】出題傾向を徹底分析したカリキュラム
-
出やすい分野・テーマを優先学習
-
出題頻度が低い範囲は最小限でOK
-
時間のない受験生にも優しい設計
【特徴2】短時間で理解できる動画講義
-
1本あたり15~20分の区切りで、スキマ時間に学習可能
-
難しい内容も噛み砕いたわかりやすい説明
-
スマホ・タブレットでいつでもどこでも視聴可能
【特徴3】ノート不要!「付箋作戦」で効率的に復習
-
テキストに付箋を貼り、試験前に重点復習できるシステム
-
ノート作成の手間を省き、インプット時間を最大化
【特徴4】本番力を養う模試+解説講義
-
模擬試験4回分を用意
-
解説動画つきで、間違いの原因分析もばっちり
【特徴5】安心のサポート体制
-
受講中は何度でも質問OK
-
疑問や不安をすぐに解消できるため、学習がスムーズに進む
■ 合格者の声も続々!
実際に受講した方からは、
「働きながらでも合格できた」
「どこを重点的に学べばいいか明確で助かった」
「勉強のモチベーションが維持できた」
といった声が多数寄せられています。
このように、本気で合格を目指す人のための講座であることが、多くの支持を集める理由なのです。
👉 詳しくはこちらからチェック!
馬淵敦士先生のケアマネ受験対策講座(公式サイト)
第5章:合格を引き寄せる勉強計画の立て方
ケアマネ試験の勉強において、ただがむしゃらに頑張るだけでは合格に届きません。
「合格から逆算して勉強計画を立てること」が、合格への最短ルートとなります。
この章では、忙しい社会人でも無理なく実践できる、効果的な勉強計画の立て方について解説します。
■ まずは試験日から逆算してスケジュールを組む
最初にやるべきことは、試験日から逆算して学習スケジュールを作ることです。
「何となく勉強を始める」では間に合いません。
【例:試験まで残り6か月の場合】
| 期間 | 内容 |
|---|---|
| 1〜2か月目 | 基礎知識のインプット(テキスト読み込み+講義動画視聴) |
| 3〜4か月目 | 問題演習スタート(過去問中心) |
| 5か月目 | 模試&弱点補強 |
| 6か月目 | 最終総復習&直前対策 |
👉 詳しくはこちらも参考に:
ケアマネ試験の合格率を上げる学習プラン
このように、月ごとに目標を決めると、着実にステップアップできる道筋が見えるようになります。
■ 毎日のノルマは「30分〜1時間」でOK
フルタイムで働きながら受験する方も多いケアマネ試験。
1日に何時間も確保するのは現実的ではありません。
だからこそ、
-
1日30分だけ講義動画を見る
-
1日1単元だけ問題を解く
など、「小さな積み重ね」でOKと割り切ることが大切です。
重要なのは、「ゼロの日を作らないこと」。
たとえ10分でも勉強を続けることで、知識の定着率は飛躍的に上がります。
■ 復習は「付箋作戦」で効率化
ケアマネ試験は範囲が広いため、復習の仕方もポイントになります。
おすすめなのが、馬淵敦士先生の講座でも推奨している「付箋作戦」です。
-
間違えた箇所や重要ポイントに付箋を貼る
-
試験直前期には付箋の箇所だけ徹底復習
こうすることで、ノート作成に時間を取られることなく、
“試験直前に見るべき場所”が一目で分かるテキストを作ることができます。
■ 模試を活用して「実戦感覚」を身につける
ケアマネ試験は時間との勝負でもあります。
本番と同じ形式・時間で模擬試験に取り組み、実戦感覚を養うことが合格には不可欠です。
-
模試は最低2〜3回は実施
-
1回ごとに間違えた問題を復習
-
「なぜ間違えたのか」を分析する
これを繰り返すことで、本番で焦らず問題を処理できる力が身についていきます。
👉 合格への近道を知りたい方はこちら:
ケアマネ試験に合格するための鉄則とは
第6章:ケアマネ試験本番までにやるべきことリスト
どんなに一生懸命勉強しても、試験本番で実力を発揮できなければ、合格は難しくなってしまいます。
だからこそ、本番直前期にどんな準備をするかが、最終的な結果を左右する重要なポイントになります。
この章では、ケアマネ試験本番までに確実にやっておきたいことをリストアップして解説していきます。
■ 1. 過去問&模試の総仕上げ
試験直前期は、新しいことに手を広げるのではなく、これまでに学習した内容を徹底的に固めることが最優先です。
【具体的な取り組み】
-
過去問をもう一度解き直す(最低でも直近3年分)
-
模試の復習ノート(付箋貼りテキスト)を読み返す
-
何度間違えた箇所は「解説を声に出して読む」ことで記憶に定着させる
特に、ケアマネ学習法の詳しい解説はこちらにもあるように、出題傾向に沿った復習が効果的です。
■ 2. 出題頻度の高いテーマを集中攻略
ケアマネ試験では、毎年必ず出題されるテーマがあります。
【出題頻度の高いテーマ例】
-
介護保険制度の仕組み
-
ケアマネジメントのプロセス
-
要介護認定や介護サービスの内容
-
医療知識(高齢者の疾患など)
これらを集中的に確認することで、得点源をしっかり確保できます。
ここは浅く広くではなく、深く・確実に理解することがカギです。
■ 3. 時間配分の最終調整
本番は120分間で60問を解く必要があります。
つまり、1問あたり2分以内で解かないと間に合わない計算です。
模試を活用して、次の感覚を身につけましょう。
-
難しい問題に固執せず、すぐ次へ進む
-
最後に見直す時間(10分程度)を確保する
-
マークミス防止に注意する
試験当日に焦らないためには、時間感覚に慣れておくことが必須です。
■ 4. 試験当日の持ち物チェックリスト
試験当日に慌てないよう、事前に持ち物をリスト化しておきましょう。
| 必須アイテム | あると便利 |
|---|---|
| 受験票 | 腕時計(スマホ不可) |
| 筆記用具(HB以上の鉛筆・消しゴム) | 飲み物・軽食 |
| 身分証明書(免許証・保険証など) | 防寒具(会場が寒い場合) |
前日夜にはすべて準備して、安心して試験に臨めるようにしておきましょう。
■ 5. メンタルコンディションの整え方
最後に、心の準備もとても大切です。
試験直前は不安になりがちですが、次のような心構えで臨みましょう。
-
「できない問題があっても合格できる」と知る
-
体調管理を最優先(特に睡眠)
-
できるだけリラックスして本番を迎える
試験は“完璧”を目指す場ではありません。
合格ラインを超えることがゴールです。
👉 本番力を高めるならこちらも参考に:
ケアマネ試験に合格するための鉄則とは
おわりに
ケアマネ試験合格は、介護業界でさらなるキャリアアップを目指す方にとって、大きなチャンスとなる資格です。
しかし、合格率15〜20%という難関を突破するためには、単なる努力だけではなく、効率的な学習戦略と適切なサポート環境が不可欠です。
本記事では、ケアマネ試験の概要から、独学と通信講座の違い、通信講座選びのポイント、さらに効果的な学習計画の立て方、試験本番までの準備方法まで、合格に直結するノウハウを網羅的にお伝えしてきました。
特に、働きながら試験勉強に取り組む方にとっては、
-
正しい順序で
-
必要な知識を効率よく
-
最短ルートで身につける
ことが成功のカギです。
その点で、馬淵敦士先生のケアマネ受験対策講座は、忙しい社会人にも最適な設計となっています。
-
短時間で理解できるわかりやすい動画講義
-
重要ポイントを絞った効率的なテキスト
-
模試と復習で確実に実力アップ
-
質問対応による安心サポート
これらをフル活用することで、限られた時間の中でも確実に合格を目指すことができます。
独学にこだわるのもひとつの方法ですが、
「本当に合格したい」
「今年こそ結果を出したい」
と強く思うなら、ぜひ通信講座の力を借りてください。
あなたの頑張りを最短距離でゴールへ導いてくれる道具は、すでに揃っています。
あとは、行動を起こすだけです。
ケアマネ試験合格という目標に向かって、今日から一緒にスタートを切りましょう!
📚 最短合格を目指すなら今すぐチェック!
👉 馬淵敦士先生のケアマネ受験対策講座(公式サイト)