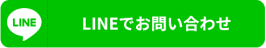ケアマネ試験の出題範囲を効率よく学ぶ!通信講座で合格を目指す方法とは?
目次
はじめに
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、介護サービスの要ともいえる存在であり、介護・医療・福祉の幅広い知識を求められる専門職です。
そのため、ケアマネ試験(正式名称:介護支援専門員実務研修受講試験)は非常に出題範囲が広く、制度や仕組みを理解していないと正答が難しい問題も多数含まれています。
「何から手をつけていいかわからない」「独学では不安」「忙しくて時間がとれない」という声は、毎年多くの受験者から聞かれます。
特に仕事や家事と両立しながら試験勉強をする方にとって、限られた時間の中で効率的に出題範囲をカバーする方法は大きな関心事です。
そこで今、多くの受験者に選ばれているのが、通信講座を活用した学習スタイル。
中でも、馬淵敦士先生の通信講座は、出題傾向に沿って作られた教材と、わかりやすい動画講義、試験に出るポイントにしぼった効率学習で、働きながらでも合格できる設計がされています。
この記事では、ケアマネ試験の出題範囲をしっかり把握し、通信講座を効果的に使って最短合格を目指すための「具体的ステップ」をお伝えします。
学習スケジュールの立て方、付箋を活用した要点整理法、直前期の復習テクニックなど、合格者が実際に行ってきたノウハウを交えながら、あなたの合格をサポートできる内容をまとめました。
また、初心者の方や試験に不安を感じている方でも安心して取り組めるように、「何から始めるべきか」「どの順番で勉強するべきか」も明確にしています。
まずは、試験の全体像と出題範囲の特徴を把握するところから始めていきましょう。
第1章:ケアマネ試験の出題範囲とよく出るテーマ
ケアマネ試験は、介護現場の経験だけではカバーしきれない、幅広い知識を問う国家試験です。
試験範囲が広く、かつ出題傾向にも特徴があるため、まずは“出るところ”を把握することが合格への第一歩となります。
■ 出題形式と分野の構成
ケアマネ試験は年に1度、10月に実施されます。試験時間は120分、全60問が五肢複択式で出題されます(5つの選択肢のうち2つを選ぶ形式)。
出題分野は大きく2つに分かれています。
-
介護支援分野(25問)
・介護保険制度
・要介護認定
・サービス利用手続き
・ケアマネジメントプロセス
・地域包括ケアシステムなど -
保健医療福祉サービス分野(35問)
・高齢者の疾病や障害の理解
・在宅医療や福祉サービス
・医療との連携、制度の知識
・生活支援や福祉施策の実務
この2分野のうち、どちらか一方でも合格基準に満たないと不合格となるため、バランスよく得点を取る必要があります。
■ 合格ラインと得点戦略
合格基準は年度により若干異なりますが、目安は以下のとおりです。
-
介護支援分野:60%前後(15問)
-
保健医療福祉サービス分野:65~70%前後(23~25問)
つまり、満点を狙う必要はありません。合格に必要なラインを見極め、確実に得点できるテーマを優先して学ぶ戦略が重要です。
■ よく出るテーマを押さえよう
出題頻度の高いテーマには以下のような傾向があります。
介護支援分野でよく出るテーマ
-
介護保険の財源構成(例:市町村25%、国25%、都道府県12.5%)
-
地域支援事業(包括的支援事業・任意事業・一般予防)
-
要介護認定の手続き・有効期間
-
居宅介護支援の基本ルール
-
サービス担当者会議とモニタリング
保健医療福祉サービス分野でよく出るテーマ
-
高齢者に多い疾患(認知症、脳血管疾患、糖尿病など)
-
在宅医療における医療機器管理(在宅酸素・吸引機・経管栄養など)
-
生活支援技術と多職種連携
-
サービスの内容と利用条件
これらは繰り返し出題されており、「試験で問われやすい=優先的に学ぶべき」項目です。
すべてを深くやる必要はなく、まずは“浅く広く”、そして出題頻度の高い部分を“深く重点的に”学ぶのが鉄則です。
■ 覚えるだけではなく“理解”が鍵
ケアマネ試験では、「この制度の目的は?」「どの手順が正しいか?」など、丸暗記では対応できない理解型の問題も多く出題されます。
そのため、効率よく学ぶには、テキストと講義動画を併用し、知識の“つながり”を意識しながら学ぶことが有効です。
馬淵敦士先生の通信講座では、こうした出題傾向に沿って、ポイントをしぼった講義・教材が提供されており、「出るところを深く」「出ないところはほどほどに」学べる設計になっています。
👉 出題傾向から学習を進めたい方はこちら:
ケアマネ受験準備についてはこちら
第2章:独学と通信講座の違いとは?合格率が変わる理由
ケアマネ試験の勉強を始めるとき、多くの人が最初に悩むのが「独学でやるか?それとも通信講座を受けるか?」という学習スタイルの選択です。
結論から言えば、独学でも合格は可能です。 ただし、その分「時間と労力がかかりすぎてしまう」という“コストパフォーマンスの悪さ”が大きなデメリットとなります。
■ 独学の現実:費用は安くても学習効率は低下しがち
独学最大のメリットは、費用を安く抑えられることです。市販のテキストや問題集を数冊購入すれば、1万円以内でも勉強をスタートできます。
また、自分のペースで学べるため、時間に縛られず自由に学習できるのも魅力のひとつです。
ですが、ケアマネ試験は制度、サービス、数値、法律など多岐にわたる知識を求められる試験。
その広範囲の内容を、何を優先して、どこまでやるべきか自分で判断するのは非常に難しいのです。
たとえ時間をかけて全体を網羅しても…
-
出題頻度の低い範囲に時間をかけてしまった
-
覚えたつもりが理解できておらず得点につながらなかった
-
正確な答えを知らずに誤学習してしまった
といったことがよく起きます。
結果として「安く済ませたけど結局不合格。翌年も受験」という事態になれば、金額以上の“時間と労力”を無駄にしてしまうことになりかねません。
■ 通信講座は「費用以上の価値」がある
それに対して、通信講座には費用がかかるものの、その投資が「時間の短縮」や「合格への近道」に直結するという大きなメリットがあります。
特に馬淵敦士先生の通信講座は、過去問に基づいた的確な出題分析と、「出るところ」に集中した講義設計が特長。
忙しい介護職や子育て世代でも、無理なく合格レベルに到達できる学習ステップが用意されています。
具体的なメリットは以下のとおりです:
-
自分で調べなくても、出題頻度が高い内容を最初から教えてもらえる
-
書籍と連動した講義動画で理解が早い
-
模試や演習問題を通じて、本番に強い実戦力が身につく
-
質問や進捗管理などのサポートもあり、不安を軽減できる
このように、「お金はかかっても、効率的に・確実に合格に近づける」という点で、通信講座の方が最終的なコストパフォーマンスは非常に高いと言えます。
■ 合格者が通信講座を選ぶ理由
実際に合格した人の多くは、講座の力を借りて学習していました。
「独学で勉強していたけど、模試の結果に不安を感じて途中から通信講座に切り替えた」
「出るところに絞った講義のおかげで、効率よく合格できた」
といった声は少なくありません。
特に、フルタイム勤務・子育て・介護などの生活との両立が必要な方にとっては、通信講座こそが“最短合格への現実的な選択肢”となるのです。
■ 独学 vs 通信講座 比較表
| 比較項目 | 独学 | 通信講座(例:馬淵敦士講座) |
|---|---|---|
| 費用 | 安い(1万〜2万円程度) | やや高め(5万〜8万円程度) |
| 学習範囲の把握 | 自分で調べる必要があり時間がかかる | 出題傾向に基づいてカリキュラムが構成されている |
| 学習効率 | 高くなりにくい(無駄な範囲に手を出す可能性) | 「出るところだけ」を集中学習でき、効率的 |
| モチベーション | 維持が難しい。孤独になりやすい | 進捗管理や定期的なサポートで継続しやすい |
| 理解度 | 誤学習に気づきにくい | 講義動画や解説で正しい知識が定着しやすい |
| 合格までの期間 | 長くなりやすい | 合格に必要な要点にしぼって短期集中が可能 |
| 不合格時の損失 | 時間も翌年分の受験料もかかる | 初年度合格の可能性が高く、結果的にコストを抑えられる |
👉 「独学に限界を感じた方」や「今年こそ合格したい方」はこちら:
ケアマネ学習法を詳しく見る
第3章:通信講座を活用した効率的な学習ステップとは?
ケアマネ試験に合格するためには、ただテキストを読み続けるだけでは不十分です。
出題範囲が広く、理解型の問題も多いため、「どの順番で、どのように学習するか」が非常に重要です。
ここでは、馬淵敦士先生の通信講座の内容をベースにした、最短合格を目指す効率的な学習ステップをご紹介します。
■ ステップ①:出題傾向を理解して“出るところ”から始める
まず最初に行うべきは、ケアマネ試験の出題傾向の把握です。
全60問のうち、約8割以上は毎年類似したテーマから出題されています。
たとえば介護保険制度、要介護認定、地域支援事業、医療系サービスなどは、**繰り返し問われる“頻出分野”**です。
通信講座では、これらの出題傾向をもとに「優先順位」を付けた講義が用意されています。
そのため、学習のスタートから的を外さず、重要な分野に集中できます。
■ ステップ②:動画講義+テキストで知識を“理解”する
次に行うのは、インプット学習です。
通信講座では、テキストと連動した動画講義が用意されているため、「読むだけ」ではなく、「見て・聞いて・考える」ことで、理解が深まります。
また、講義中に「この数値はよく出ます」「この流れは押さえておきましょう」といった指示があるため、受講生はその場でテキストにマークを付けたり、付箋を貼って重要ポイントを整理できます。
このように、学習に“選択”と“集中”を持たせることが、効率学習のカギです。
■ ステップ③:付箋作戦で復習効率を高める
馬淵先生の講座で推奨されている「付箋作戦」は、復習の効率を飛躍的に上げるテクニックです。
学習中に出てきた重要ポイントに付箋を貼り、短く要点を書くことで、試験前には“貼った付箋だけ”を見返すだけで復習が完了します。
色分け(制度・数値・手続きなど)をしておけば、情報を一目で分類できるのも大きなメリットです。
■ ステップ④:問題演習と模試で“本番対応力”をつける
知識を定着させるには、アウトプット(問題演習)が欠かせません。
通信講座では、各単元ごとに演習問題があり、さらに模擬試験もセットになっているため、実践形式で自分の理解度を確認できます。
問題演習→間違えた箇所に付箋→復習というサイクルを繰り返すことで、「弱点を強みに変える」学習が可能になります。
■ ステップ⑤:スケジュールと習慣化で継続力アップ
どれだけ教材が良くても、続けなければ合格はできません。
通信講座では、週ごとの学習スケジュールや、達成チェック機能も整備されており、「今日何をやればいいか」が明確にわかるのが大きな安心ポイントです。
毎日30分の学習でも、6か月継続すれば約90時間。
さらに休日の集中学習を組み合わせることで、十分に合格ラインに到達できます。
👉 「効率よく学ぶための流れを知りたい方はこちら」:
ケアマネ試験の合格率を上げる学習プラン
第4章:出題範囲をカバーするスケジュール戦略
ケアマネ試験は、全60問・五肢複択という形式で、出題範囲は介護保険制度から医療・福祉サービス、倫理的視点まで非常に幅広い内容をカバーします。
そのため、「何をいつ学ぶか」というスケジューリングが合格に直結する要素となります。
この章では、限られた時間で合格ラインに達するための現実的なスケジュール戦略をご紹介します。
■ 学習開始は「6か月前」が理想
一般的に、ケアマネ試験対策には150~200時間程度の学習時間が必要と言われています。
1日1時間の学習時間を確保できれば、約半年で合格レベルに到達可能です。
もちろん、スタートが早ければ早いほど余裕が持てますが、重要なのは「スケジュールに合わせた戦略的な進め方」です。
■ 6か月モデルの学習スケジュール例
| 月数 | 目的 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1か月目 | 全体像をつかむ | テキスト読解+講義動画視聴 | 出題範囲・制度の理解を深める |
| 2〜3か月目 | 頻出項目の集中学習 | 重要ポイントに付箋・演習スタート | 「付箋作戦」で記憶の可視化 |
| 4か月目 | 演習とアウトプット強化 | 分野別問題演習+模試 | 自分の弱点を把握する時期 |
| 5か月目 | 苦手潰しと模試対策 | 模擬試験+間違い復習 | 精度を高める学習へシフト |
| 6か月目 | 総仕上げ | 付箋の見直し+要点整理 | “得点源”にしぼった復習で対策完了 |
このモデルをもとに、「自分の生活スタイルに合った学習計画」を立てることが大切です。
たとえば、夜勤がある方や子育て中の方は、週単位のタスクで調整すると無理がありません。
■ 3か月モデル(短期集中)のポイント
受験日が迫っている場合は、3か月の短期集中モデルも現実的です。
| 月数 | 学習内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 1か月目 | 頻出ポイントに絞って学習+付箋貼り | 「覚えるより見つける」戦略に切り替える |
| 2か月目 | 問題演習+模試+要点再整理 | アウトプット中心に切り替え |
| 3か月目 | 付箋中心の繰り返し+暗記強化 | 見たことがある情報を増やす反復期間 |
この短期戦略の要は、「出ないところはやらない勇気」「出るところだけ深くやる判断」です。
そのためにも、出題傾向を熟知している馬淵敦士先生の通信講座のようなサポート付き講座を活用するのが効果的です。
■ スケジュール管理におすすめの工夫
-
カレンダーアプリに「今日やること」を入力
-
学習日誌をつけて進捗を見える化
-
付箋の枚数で“頑張った実感”を可視化
-
月1回の「自分模試日」を設定する
習慣化と視覚化の工夫を組み合わせることで、モチベーションも維持しやすくなります。
👉 ケアマネ受験に向けた準備についてはこちら:
ケアマネ受験準備についてはこちら
第5章:合格者に学ぶ!出題範囲の攻略と“やらない”戦略
ケアマネ試験の出題範囲は広く、全てを完璧に学ぼうとすると、膨大な時間と労力が必要になります。
しかし、実際に合格している人たちは、すべてを完璧に覚えているわけではありません。
彼らに共通するのは、「やるところ」と「やらないところ」の見極めがうまかったことです。
この章では、出題範囲を効率よく攻略するために必要な“取捨選択”の視点と、合格者が実践していた具体的な工夫を解説します。
■ 出題傾向をもとに「やるべき」と「やらない」を分ける
ケアマネ試験は五肢複択60問の中で、出題されやすい“得点源”と、出題頻度の低い“捨て問候補”が存在します。
たとえば以下のような分野は出題頻度が高く、重点的に学習すべき項目です。
-
介護保険制度の財源(国・都道府県・市町村の負担割合など)
-
要介護認定のプロセス(一次判定・主治医意見書・認定審査会)
-
地域支援事業の構成と役割(包括的支援事業・一般予防・任意事業)
-
サービス担当者会議やケアプラン作成の流れ
-
高齢者によくある疾病(認知症、糖尿病、脳血管疾患など)
一方で、以下のような細かすぎる数字や、実務では重要でも出題頻度が低い項目については、深く学習しないという選択も必要です。
-
各市町村独自の取り組み(任意事業の細部)
-
地域密着型サービスなどの細かな加算要件
-
地域包括支援センターの業務の細部
これらを無理に覚えようとすると、時間だけが奪われ、合格に直結する部分の復習ができなくなる可能性があります。
■ 合格者が実践した“やらない戦略”とは?
実際に合格した受験生の多くは、以下のような工夫で出題範囲の取捨選択を行っていました。
-
「過去問に一度も出ていないものは後回し」
-
「テキストに付箋を貼った箇所しか復習しない」
-
「出題傾向表を見て、優先順位を毎週調整する」
-
「“知らなくても点が取れる”問題は捨ててもよいと割り切る」
つまり、彼らは“完璧を目指さないこと”こそが、完走するための最短ルートであると知っていたのです。
■ 通信講座だからできる「出るところだけ」の徹底学習
馬淵敦士先生の通信講座では、20年以上の出題分析をもとに、“出るところ”だけを集中して学べる仕組みが整っています。
また、重要ポイントには講義中に「出るぞマーク」があり、迷うことなく優先順位がつけられるため、自然と“やらない勇気”が持てるようになります。
さらに、講座では「出ないところはやらなくていい」と明確に言い切ってくれるため、勉強の方向性にブレがなく、挫折のリスクも減ります。
👉 合格に必要な情報だけに絞って学びたい方へ:
ケアマネ試験に合格するための鉄則とは?
第6章:試験本番に向けた直前対策と心構え
どんなに準備をしていても、試験本番が近づくと不安はつきものです。
「覚えきれていない」「あれもこれもやっておくべき?」と焦りが生まれ、かえって集中力が落ちてしまうこともあります。
この章では、ケアマネ試験の直前期(試験1か月前〜当日)にやるべきこと、やらなくていいこと、そして本番で力を発揮するための心構えを整理してご紹介します。
■ 直前期にやるべきこと:復習の“絞り込み”
直前期の勉強は、“広く浅く”ではなく、“狭く深く”が鉄則です。
ここで新しい参考書に手を出すのはNG。いままでやってきた教材を、いかに深く見直せるかが合否を分けます。
以下のような流れで復習するのがおすすめです。
-
自分が付箋を貼った箇所だけをピックアップして復習
-
模試や過去問で間違えた問題の再確認
-
出題頻度が高いテーマを総ざらい(介護保険制度、要介護認定、在宅医療など)
この時期に「全部やろう」とすると、かえって焦ってパフォーマンスが下がってしまいます。
“覚える”よりも“忘れない”ための確認作業に集中しましょう。
■ 本番直前の“やらない”ことリスト
-
新しい教材に手を出す
-
周りの人と自分を比較する(特にSNS・オープンチャット)
-
覚えていない細かい部分に執着する
特にSNSやオープンチャットでは、「私は模試で○○点取れました」といった投稿が不安を煽ります。
そうした情報からは意識的に距離を取りましょう。今は自分の学びを信じる時間です。
■ 試験当日のチェックポイント
-
前日は早めに就寝。夜ふかしの暗記は逆効果
-
持ち物を前日までにチェック(受験票、鉛筆、時計、上着など)
-
当日はテキスト全体を読むのではなく、付箋を貼った要点だけを見返す
-
開始前は深呼吸。「見たことある情報を探す」気持ちで臨む
ケアマネ試験は60問すべて正解する必要はありません。
6〜7割の正答率で合格できるため、わからない問題は時間をかけずに飛ばし、「取れる問題を確実に取る」ことに集中するのがポイントです。
■ 合格する人の共通点は「焦らないこと」
過去の合格者に共通しているのは、試験当日に焦らず“今までやってきたことだけで勝負する”という心構えを持っていたことです。
そしてそのためには、事前に「ここまでやった」「これで大丈夫」と思える学習の積み重ねが必要です。
馬淵敦士先生の通信講座では、試験当日の心の持ち方まで解説しており、受講生が安心して試験に臨めるようにメンタル面でもサポートが整っています。
👉 最後の総仕上げに:
ケアマネ試験の合格率を上げる学習プラン
おわりに
ケアマネ試験は、出題範囲の広さ、試験形式の特殊さ、そして受験者の多くが働きながら勉強しているという状況から、「時間の使い方」と「学習の効率化」が問われる資格試験です。
この記事では、出題範囲の傾向と学習の優先順位、独学と通信講座の違い、効率的な学習ステップやスケジューリング、さらに合格者が実践していた“やらない戦略”までを体系的にご紹介してきました。
どれも、「限られた時間でも、確実に合格を目指す」ための実践的な知恵です。
中でも、馬淵敦士先生の通信講座は、これまでに多くの受講生を合格へ導いてきた実績を持つ信頼の講座です。
試験に出るところにしぼった講義、理解が深まるテキスト、効率よく復習できる付箋活用法、さらに直前期のサポートまで、すべてが「最短合格」のために設計されています。
独学でも合格は可能ですが、そのためには膨大な時間と労力がかかり、方向性のズレや不安によって途中で挫折するケースも少なくありません。
「効率よく、確実に合格を目指したい」そう考える方にこそ、通信講座の活用は最適な選択肢といえるでしょう。
そして、何より大切なのは、“自分を信じて学習を続けること”。
焦らず、他人と比べず、毎日の積み重ねを大切にしていけば、必ず結果はついてきます。
ケアマネ試験合格という目標を、ぜひ現実のものにしてください。
あなたの挑戦を、心から応援しています。
👉 通信講座の詳細はこちらから:
🔗 ベストウェイケアアカデミーのケアマネ受験対策講座